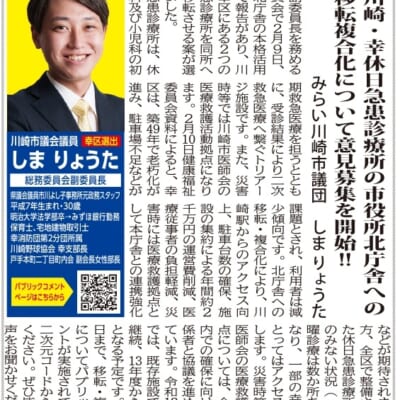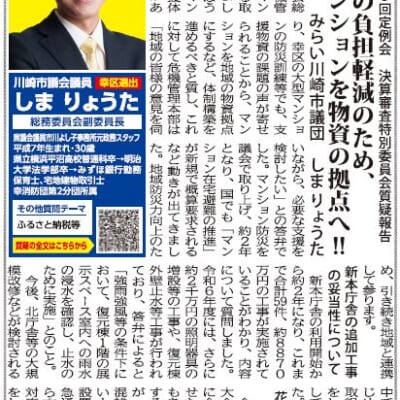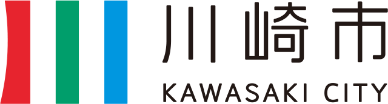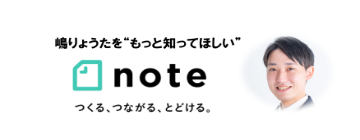マンション防災について
しま:それでは、通告に従いまして、一問一答にて伺ってまいります。
はじめに、本市のマンション防災について伺います。
まず、地域防災計画震災対策編修正素案についてです。
昨年12月定例会一般質問にて、マンション防災の質問の中で、地域防災計画の見直しについて、明確に在宅避難を盛り込むことを要望し、今回の修正素案では、新しく「在宅での避難の考え方の啓発等」という形で盛り込まれることとなりましたが、その経緯について伺います。
危機管理監:在宅での避難に関する御質問でございますが、自宅が倒壊や火災、浸水等の恐れがなく、安全に利用 できる場合には、在宅での避難も有効であることから、国が本年6月に行った防災基本計画の修正において在宅避難者等に対する支援が明記されたこと等も踏まえ、本市におきましても、現在、在宅での避難の考え方の啓発等に関する新たな記載も含めた「川崎市地域防災計画震災対策編」の修正素案をお示しし、パブリックコメント として広く御意見を募集しているところでございます。以上でございます。
しま:次に、関連して地区防災計画についてです。今回、策定された幸区の東小倉地区 防災計画のように、町会・自治会単位での策定が想定されます。11月15日総務委員会の報告時には、地区防災計画策定について、「予算は決まったものがない」との説明がありましたが、例えば、有識者を招いて策定した場合の費用や策定後の町内に配布する際の印刷費等は、町内会・自治会活動応援補助金等の何らかの補助金の対象になるのか本市の見解と対応を伺います。
危機管理監:地区防災計画についての御質問でございますが、地区防災計画は、地域防災力を高めて、地域コミュニティを維持・活性化することを目的に作成されることから、各自主防災組織など災害対応に携わる団体に対して有効であると考えております。
地区防災計画の策定支援といたしましては、資料の作成や配布については、自主防災組織を対象とした助成制度として、川崎市自主防災組織活動助成金」において対象となっており、また、市民文化局では、「川崎市町内会・自治会活動応援補助金」の制度がございまして、講師謝礼金や印刷費等が補助金の対象となると伺っております。以上でございます。
しま:自主防災組織の活動助成金と、町内会・自治会の活動応援補助金がどちらも使えるとのことでした。あわせて、周知をお願い致します。
次に、マンション防災の啓発についてです。同じく昨年12月一般質問にて、マンション防災に特化した啓発を要望しましたが取組状況について具体的に伺います。また、課題もあわせて伺います。
危機管理監:在宅での避難の啓発についての御質問でございますが、マンションや集合住宅などは、一般的に、木造住宅より倒壊する可能性が低いものの、長周期地震動による家具転倒など特有のリスクもございますことから、「在宅での避難のススメ」と題しまして、在宅での避難の考え方やマンション防災の取組事例等につきまして、改めて、 関係局区の取組を横断的にまとめたホームページを作成したことを始め、啓発冊子「備える。かわさき」への記載の充実や、広報用動画を新たに作成するなど普及啓発に取り組んでいるところでございます。
一方で、在宅での避難の考え方等の啓発を進めるにあたりましては、災害発生時には、地域ごとに被害状況やインフラ等の途絶期間が異なることが想定されるほか、各地域におけるコミュニティの状況等を考慮する必要もございますので、今後も、地域の実情を踏まえながら、関係局区等と連携して取り組んでまいります。以上でございます。
しま:様々取組を進めていただき、ありがとうございます。引き続き、地域に合わせた啓発や課題ということですので、きめ細かな対応、支援をお願い致します。
次に、関連して「川崎市ぼうさいチャンネル」についてです。答弁の広報用動画がYouTube「川崎市ぼうさいチャンネル」にて配信されていますが、チャンネル登録者数が今朝の時点で、272人、今年度新しく作られた広報用動画の再生回数も数百回程度となっています。マナビーとニャビ先生といった可愛らしいキャラクターのアニメーションであり、子どもにもわかりやすく、大人も勉強になる内容です。例えば、学校でのGIGA端末での視聴や、関連する授業での活用も有意義な啓発と考えますが本市の見解と対応を伺います。
危機管理監:防災啓発動画についての御質問でございますが、デジタルコンテンツによる防災啓発として、YouTube「川崎市ぼうさいチャンネル」において、市民の皆様に防災を身近なものとして取り組んでいただけるようなアニメーション動画を配信しております。
今年度は毎月1回のペースで配信しており、SNSや「備える。かわさきマガジン」等により広報しておりますが、チャンネル登録者数や再生数が課題となっているところでございます。
このような状況の中、学校現場におけるGIGA端末での視聴や防災教育での活用は、次代を担う子どもたちをはじめ、親子で防災を考える機会として大変有意義なものと考えておりますので、関係局区と連携しながら取組を進めてまいりたいと存じます。
しま:能登半島地震からまもなく1年となります。そうした機会でもありますので、早めの対応をお願い致します。
次に、マンション防災におけるエレベーター対策についてです。先月の報道において「東京都の首都直下地震によるエレベーターの被害は16万6000台のうち、最大2万2400台以上で人が閉じ込められ、救助に長い時間がかかると見られる」とされており、同じく共同住宅が多い本市においてもエレベーターの防災対策は大きな課題と考えられます。
はじめに、首都直下地震等の大規模災害時におけるエレベーター閉じ込めに対する消防機関による救助の対応について消防局長に伺います。また、課題及び現在の取組について伺います。
消防局長:消防機関によるエレベーター対策についての御質問でございますが、地震時の消防活動につきましては、消防局で策定している、震災警防基本計画に基づき活動を行うこととしており、災害規模に応じ、全職員により全消防力をもって消火活動を最優先として、対応することとしております。
エレベーター閉じ込めにおける対応の課題といたしましては、大規模地震時には同時多発的に発生する、全ての災害に直ちに対応できない状況が考えられますことから、救出までには時間を要することが想定されます。
また、対応につきましては、保守事業者と連携し活動を行いますが、メーカーごとに構造や形状が異なり、危険も伴うことから専門的な知識と機材が必要となります。 このため、特別の技術教育を受けた職員が対応することが必要となり、毎年各消防署の救助隊員に対して、一般 社団法人日本エレベーター協会が開催する専門的な研修を受講させ、技術の習得に取り組んでいるところでございます。
しま:人を充てるのが難しい可能性があること、また、専門性が必要であることがわかりました。
次に、防災訓練等の取組についてです。保守事業者と答弁の通り救助隊では、早期の救出が難しいことが容易に想定されます。国土交通省の「千葉県北西部地震におけるエレベーターの被害状況等について」の資料では、保守事業者等は、「復旧の優先順位を定めた物件の一覧表の作成や優先すべき用途の設定を実施」し、それをもとに、「各社が復旧作業を実施した」とのことです。限られた人員で、多くの命を助けるためには、住民理解を促し、協力を得ることが重要です。港区では、区が主催となり、タワーマンションにて保守事業者の指導のもと、住民が自ら建物側からエレベーターのドアを開ける訓練が行われています。また、今年度から「エレベーター閉じ込め対応訓練」の募集が始まり、訓練時間中はエレベーターを停止させ、保守事業者の説明と指導をもとに訓練の実施が進められています。まず、大規模災害時のエレベーター閉じ込めに対する本市の見解を伺います。また、こうした防災訓練等を含めたエレベーター対策の普及啓発を求めますが、本市の見解と対応を伺います。
危機管理監:エレベーターの防災対策についての御質問でございますが、本市におけるマンション等の集合住宅に住む世帯は、令和2年度の国勢調査結果では7割を超えておりますことから、大地震等により、多くのエレベーターが同時に停止した場合、保守事業者の対応に時間を要するなど、 閉じ込めが長期化する可能性もございますので、エレベーターに閉じ込められた際の対応を市民の皆様にあらかじめ御理解いただくことは重要と考えております。こうした考えの下、これまで「備える。かわさき」等 において、閉じ込められた際の対応や、マンション管理会社と災害時の対応についてあらかじめ確認しておくこと、エレベーター内の備蓄や、エレベーターに閉じ込められた人がいないか確認するなどの啓発に取り組んできたところでございます。今後は、閉じ込められた際の対応を訓練内容に取り入れることを御案内するなど、実際の状況をイメージし、一人一人が自分事として備えていただけるよう、関係局区等と連携しながら、更なる啓発に取り組んでまいります。
しま:エレベーターの訓練自体まだ事例が少ないということもありますが、他都市の事例等を調査していただき、案内だけでなく、防災訓練の一つのパッケージとして本市から提案、または予算的な補助も含めた後押しを検討することを要望致します。引き続き注視して参りたいと思います。
コミュニティ交通及びモビリティハブについて
しま:次に、コミュニティ交通とモビリティハブについて伺います。モビリティハブについては、他会派代表質問で大方理解致しましたので、別の観点で質問したいと思います。
はじめに、モビリティハブの今後の取組の考え方を伺います。
本市が期待するモビリティハブの役割のひとつとして、「地域のにぎわいの創出」がありましたが、そうしたことも担っていくのであれば、モビリティハブの考え方を踏まえた上で、コミュニティ交通の充実に本市も予算措置を含め、より注力していくべきと考えます。例えば、既存路線バスを考慮した上で、本市が主体となって、「地域のにぎわいの創出」を目的としたモビリティハブの実証実験と称し、試験的な導入を実施することが検討される可能性があるのか伺います。
まちづくり局長:モビリティハブについての御質問でございますが、本市におきましては、現在、民間事業者と連携したモビリティハブの実証実験を実施しており、路線バスやコミュニティ交通などの多様なモビリティが利用できる乗換機能の形成とともに、利用者の乗換負荷の軽減を目指し、にぎわい創出イベントをあわせて開催しているところでございます。
今後につきましても、多様なモビリティが利用できる機能ととともに、地域のにぎわいの創出や移動の目的地ともなり得る拠点の形成を進めることで、地域で生活しやすい環境が構築できるよう、民間事業者や地域等と連携を図りながら、検討を進めてまいります。
しま:「民間事業者や地域等と連携を図りながら、検討を進めていく」ということでございますので、残りは、本市でありますから、市が主体となって進めていくことを検討していると理解いたしました。コミュニティ交通に関する取組の中でも、仮に本市がアクションを起こしていくとなれば大きな進歩だと思いますので、ぜひ取り組みを進めていただくよう強く要望致します。
次に、幸区におけるコミュニティ交通の試行実施についてです。令和5年第3回定例会一般質問では、市民アンケート調査より幸区の高齢者の約2人に1人は、「自分が自由に使える車等が無く、送迎してくれる家族等も近くにいない」という結果で、他の区より多いことが明らかになりました。モビリティハブ実証実験前までは、幸区以外の各区でコミュニティ交通の実証実験等が行われており、今回、初めて幸区が範囲となりましたが、2店舗のカーディーラーに停まるのみです。一方で、幸区内で実際にコミュニティ交通車両が走り始め、また店舗でイベント等も行われていることから、区民の関心が高まってくることが想定されます。幸区でのコミュニティ交通の実証実験等の実施の検討を求めますが、本市の見解と対応を伺います。
まちづくり局長:コミュニティ交通についての御質問でございますが、本市のコミュニティ交通の取組につきましては、路線バスを利用しづらい住宅地から鉄道駅・生活施設等までへの移動を補完する交通であり、令和4年3月に取りまとめた「コミュニティ交通の充実に向けた今後の取組」に基づき、地域の主体的な取組や新技術、新制度を活用した民間事業者と連携したデマンド交通の取組など、地域特性に応じた支援を行っているところでございます。
この度の「チョイソコかわさき」の実証実験におきましては、カーディーラーを活用した「モビリティハブ」の実現性について、事業主体と関係事業者による調整の結果、幸区内の2店舗を含む4店舗について、実証実験を行っているところでございます。
幸区へのコミュニティ交通の導入につきましては、既存交通との整合を図りながら、地域特性に応じた支援を行ってまいります。
しま:幸区の高齢者の現状や要望する声が長年寄せられていることから、求めたものであります。現在検討されているモビリティハブのコミュニティ交通の取組においては、本市が主体となって、幸区の状況を踏まえた実証実験等の検討を要望します。
最後に、お隣の横浜市では、12月11日定例会本会議にて、「データを用いて、交通空白地域を抽出し、客観的データを基にした運行計画の提案を行政がプッシュ型で行っていく」旨の市長の答弁でありました。背景には、路線バスの減便の影響があると推察されますが、「外出促進、生活の質の向上、にぎわいの創出を通して街の価値向上」のためとの言葉もありました。本市の交通施策、コミュニティ交通においても、今後の社会情勢を踏まえた抜本的な考え方の見直しを要望し、次の質問に移ります。
JR東日本南武線連続立体交差事業及び矢向駅周辺の利便性向上等について
しま:次にJR南武線連続立体交差事業と矢向駅周辺の利便性向上等について伺います。
昨年12月定例会一般質問では、矢向駅の周辺人口の増加と安全性を踏まえた利便性向上について伺ってまいりました。この度、南武線連続立体交差事業もまもなく事業認可取得見込みであり、来年から用地取得が始まっていく中で、改めて矢向駅の状況について確認してまいります。
はじめに、他会派の代表質問にて、オープンハウス型説明会での主な質問の中に「横浜市域である矢向駅周辺の立体交差化について」があったとのことですが、具体的な質問の内容と回答を伺います。また、回答した際の住民の反応について伺います。あわせて、説明会を通して見えた課題と対応について伺います。
建設緑政局長:JR南武線連続立体交差事業についての御質問でございますが、オープンハウス型説明会につきましては、地域の皆様への本事業の取組状況などの周知のため、本年11月に開催したところでございまして、矢向駅から鹿島田駅間において、高架から地表に擦り付ける計画に対して、「横浜市域の尻手駅から矢向駅間も立体化してほしい」との御質問が一部の来場者からございました。その回答といたしましては、「横浜市の踏切整備計画において、南武線矢向駅周辺ほか4区間を連続立体交差候補区間として位置付けられているものの、平成28年3 月に公表した踏切安全対策実施計画において、相模鉄道本線鶴ヶ峰駅周辺を最も優先的に事業化の検討を進める区間としたことから、本市としては、事業認可の取得後、工事着手まで5年程度見込んでいるため、横浜市域と本市域の同時完成に向けて協力を求めている」と説明した ところでございます。
来場者からは、横浜市の踏切計画の状況等を初めて知ったなどの反応があり、本市の説明によって一定の御理解をいただけたものと考えております。今後につきましては、説明会での来場者の反応から、本事業の取組状況の詳細に加えて、横浜市の計画等についても丁寧に説明することが必要であると再認識したところでございますので、引き続き、様々な機会を通じて取組状況などの周知に努めてまいります。以上でございます。
しま:矢向駅周辺の方々とお話をすると、矢向駅が立体交差化されないことは一部の詳しい方は知っているが、知らない人も多いのが実感です。計画区間が矢向駅から武蔵小杉駅までと記載されることから、正しく理解されている方が多くないのだと推察します。細かい部分ではありますが適切な周知に努めていただくよう要望致します。
次に、矢向駅周辺の立体交差化についてです。オープンハウス型説明会でも複数意見が寄せられていたとのことでした。また、9月には、お隣、横浜市鶴見区の生見尾踏切、今月5日には、幸区内の鹿島田踏切にて、人の命が失われる悲惨な事故が続いています。安全な交通環境を構築していくためにも、矢向駅周辺の立体交差化の必要性は増すばかりでありますが、本市の横浜市への働きかけの状況と、今後の取組について伺います。
建設緑政局長:JR南武線連続立体交差事業についての御質問でございますが、横浜市域の矢向駅周辺につきましては、本事業は、本市域の矢向駅から武蔵小杉駅までの区間について、本年8月に都市計画決定を行ったところでございまして、事業認可の取得後、工事着手までに5年程度を見込んでいるため、横浜市域と本市域の同時完成に向けて横浜市に協力を求めているところでございます。
今後につきましても、横浜市・川崎市道路行政連絡会議など様々な機会を活用し、横浜市域と本市域の同時完成に向けて、引き続き、横浜市に協力を求めてまいります。
しま:事業認可取得後も、引き続き働きかけをして頂くことを改めて確認させていただきました。来年から実際に用地取得が始まると、更地もでき、街の雰囲気も少しずつ変わり、それにあわせて周辺住民の関心も高まり、意識も変わってくると思われます。引き続き、横浜市への根気強い働きかけをお願い致します。また、本市のオープンハウス型説明会の主な質問及び回答等の資料には、「矢向駅の東側にも改札口を設置して欲しい。」との意見もあったと記載されています。踏切の除去が第一でありますが、そうした意見があったこともあわせて伝えていただくことも要望します。
新多摩川プラン及び多摩川に関する施策について
しま:次に、新多摩川プラン及び多摩川に関する施策について伺います。
はじめに、多摩川の利用に関するアンケート調査についてです。前回の一般質問にて、アンケート調査の時期と回答手法について質問し、「異なる季節に実施することも有効と考え、調整していく」旨の答弁でした。アンケート調査についてのこれまでの調整の経緯及び実施方法、時期について検討状況を伺います。
建設緑政局長:多摩川の利用に関するアンケート調査についての御質問でございますが、本調査につきましては、昨年12月から本年3月まで 実施したところでございまして、異なる時期の調査も必要と判断し、本年秋に2回目の実施を予定しておりましたが、8月29日からの大雨により、多摩川緑地の運動施設等に大きな被害が発生したため、調査を延期したものでございます。
また、本年8月に開催した川崎市多摩川プラン推進会議において、アンケート調査に対する御意見をいただき、これを踏まえて、調査結果の比較が出来るよう前回と同様の調査方法と内容を基本としつつ、新たな調査項目についても検討を進めているところでございまして、次回 の調査については、来年5月頃に実施してまいりたいと考えております。
しま:着実にお願い致します。
次に、新多摩川プランの改訂についてです。最初の多摩川プランは、平成19年3月に策定され、平成27年度の平成28年3月までの10か年の計画でした。その後、新多摩川プランが平成28年3月に策定され、同じく令和7年度の令和8年3月までの計画となっています。平成27年12月10日のまちづくり委員会報告では、「改定に向けて、平成26年度から多摩川プラン推進会議や庁内推進会議でとりまとめてきた」とのことです。多摩川プラン推進会議議事録では、平成25年度2月に、議事として「多摩川プランの改訂に向けて」があり、議論が始まっています。今回の改訂についても、令和5年度8月の多摩川プラン推進会議議事録にて議論が確認できますが、令和9年度までの緑の基本計画との調整等について話されています。新多摩川プランの改訂について、推進会議の議論から、現在までにおける庁内での検討状況を伺います。また、目標年次の10年目となる来年度の取組について伺います。
建設緑政局長:新多摩川プランについての御質問でございますが、本市の附属機関である「川崎市多摩川プラン推進会議」につきましては、令和5年度は会議を2回、今年度は1回開催したほか、改定に向けた勉強会として現地視察なども実施したところでございます。
来年度の取組につきましては、現計画10年間の総括評価を行うとともに、令和9年度には「川崎市緑の基本計画」の改定を控えており、また、国で変更を予定している「多摩川水系河川整備計画」等の関連計画の検討状況や、社会環境の変化なども踏まえ、今後の多摩川プランのあり方について整理してまいりたいと考えております。
しま:しっかり、整理していただくのとともに、議会への報告をお願いいたします。
次に、新多摩川プランの改訂における市民の意見聴取についてです。平成27年12月10日のまちづくり委員会では、前回の新多摩川プランの改訂に向けて、「河川敷のイベントに出かけて市民アンケートをとる」「インターネットで募集する」「ラジオでアンケートの広報をする」等の取組を経て、328件の意見を収集したとのことです。これまで大型台風等の水害被害や、コロナ禍などを経て、今回10年に1度の改訂にあたるうえで、多くの市民の声を拾うことが重要です。地域住民、利用団体等を含め、丁寧な意見聴取を求めますが、本市の見解と対応を伺います。
建設緑政局長:新多摩川プランについての御質問でございますが、改定に向けた意見聴取につきましては、多摩川は川崎のシンボルである「ふるさとの川」として、市民共有の財産であり、様々な分野において多くの市民が活動を行っておりますことから、広く市民の皆さまや、関係団体等からも御意見をいただけるよう意見聴取の方法を検討してまいります。
しま:着実にお願い致します。
次に、関連して、多摩川河川敷にある小向の練習馬場の跡地活用についてです。
現在、移転が検討されているところではありますが、プランの改定時期等によっては、移転後の跡地活用についても議論される可能性が想定されます。令和6年第2回定例会我が会派代表質問では、「跡地活用については、スポーツ施設の整備など市民ニーズを踏まえた上で、国をはじめとする関係者に対し早期に働きかけを行うよう」要望しました。働きかけを行う上で、地域住民や利用者、団体などの市民ニーズを含めた本市の意向をしっかりまとめることが重要と考えますが、本市の見解と対応を伺います。
建設緑政局長:新多摩川プランについての御質問でございますが、多摩川水系河川整備計画におきましては、具体的な利用または保全の内容を示す機能空間区分が国により設定されているところでございまして、将来的には、小向地区の区分変更も想定されますことから、状況を注視し、 関係局と連携を図りながら、必要に応じて対応を図ってまいりたいと考えております。
しま:想定外の場合は、対応が必要な時ですのでしっかり対応お願いしたいと思います。
前回、一般質問でも幸区の河原町グラウンドが使えなくなることから代替機能の確保の為、活用を求めました。全体的にまだまだ庁内の議論が進んでいないように見受けますが、しっかり進めていただくようお願いいたします。また、答弁の「多摩川水系河川整備計画」は、つい先日10月31日の国土交通省関東地方整備局有識者会議で、今後の計画策定の流れが示されました。これからまさに計画が作られていく中で、関係都県会議、国の有識者会議と議論がなされていきますが、情報収集等アンテナを張っていただくのはもちろんのこと、今回の小向地区に限らず、本市市民にとって十分な利益にならない議論になりそうなときには、関係局が連携し、前持った働きかけを強く要望致します。そのためにも、意見聴取が重要です。プラン改定に向けて行うとのことですが、本市市民の考え、意向を丁寧にとりまとめていただくよう要望致します。引き続き、注視していくことを申し上げまして、質問を終わります。