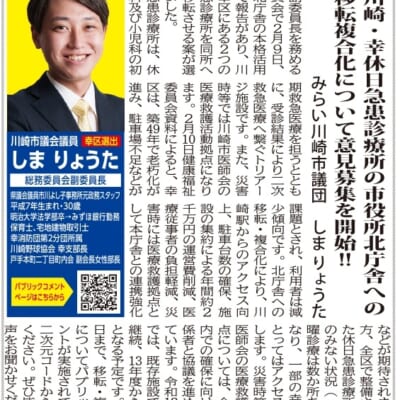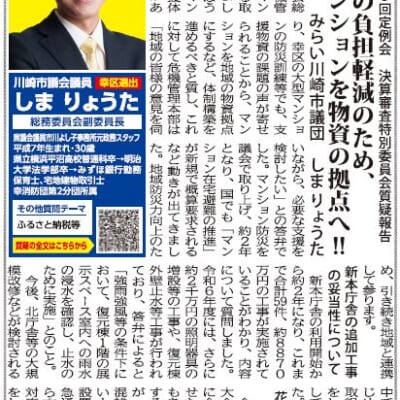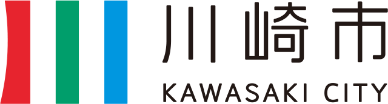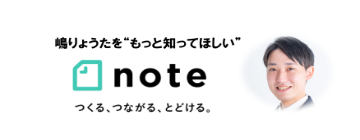副議長 36番、押本吉司議員。
押本:私は、みらい川崎市議会議員団を代表して、令和6年第2回定例会に提案されました諸議案並びに市政一般について質問をいたします。
押本:私は、みらい川崎市議会議員団を代表して、令和6年第2回定例会に提案されました諸議案並びに市政一般について質問をいたします。
先月28日、登戸児童殺傷事件から5年が経過しました。この事件をきっかけに、2022年、本市は犯罪被害者等支援条例を施行しましたが、当初、議会に示された条例案は、他都市の後発にもかかわらず、他都市と横並びの支援内容に終始し、児童生徒のケアや通学ができなかった場合の継続した教育支援など、登戸事件を教訓とした、凄惨な事件が発生した本市だからこその条例を策定すべきと当局の姿勢をただしました。当時の文教委員会の質疑や、議案に対する修正案の提出、討論の実施など、各会派からの熱心な議論の結果、予定していなかった教育支援メニューの拡充が図られたところです。当時の議会と行政のやり取りは、本来の二元代表の在り方、市政運営の両輪のあるべき姿です。我が会派は、事件を風化させることなく、犯罪被害者等をはじめ、市民の生命、財産を守るという市民代表としての役割を常に自問自答し、次の100年後の市民に対して恥じることのない議会の姿を全力で追求することをここに表明し、以下、質疑してまいります。
初めに、特別市実現に向けての取組を伺います。5月20日に第58回指定都市市長会議が開催されました。特別市の早期実現に向けた法制化への機運醸成が大きなテーマであったと仄聞します。これまで取り組んできた国、国会議員、経済界等への働きかけを今後どのように強化していくのか具体的に伺います。
市長:それでは、私から、ただいまみらいを代表されました押本議員の御質問にお答えいたします。
特別市についての御質問でございますが、初めに、国や国会議員、経済界等に対する働きかけにつきましては、昨年11月の指定都市市長会の提言に加えて、新たな提言案を取りまとめることや、指定都市を応援する国会議員の会の開催を呼びかけること、さらには経済同友会との意見交換を優先的に行うことなど、具体的な取組を進めることとしております。
押本:次に、地方制度調査会の活用についてです。既に市長が座長を務める多様な大都市制度実現プロジェクトの会議においても俎上に上がったと仄聞しますが、これからの取組について伺います。
市長:次に、地方制度調査会につきましては、大都市制度の在り方について調査審議が行われるよう、今月5日に、本市の国の予算編成に対する要請の中で、私自ら松本総務大臣に直接要請をしたところでございます。今後、指定都市市長会の多様な大都市制度実現プロジェクトにおいても議論を重ね、次期地方制度調査会を見据えた指定都市市長会としての主張をタイムリーに発信していきたいと考えております。
押本:次に、機運醸成と周知についてです。本市においてもいまだ不十分と感じます。その要因について具体的に伺います。また、県と指定都市間で生じている受益と負担のねじれの視点を最大限強調し、その改善策として特別市という新たな自治体の形を提示していくことが有効と考えますが、見解を伺います。
市長:次に、特別市の機運醸成等についてでございますが、自治の在り方全般に関する制度であることから、より分かりやすい広報が必要だと考えているところでございます。特別市制度の必要性を効果的に伝えていくため、市民の納めた県税がどのように使われているかなど、大都市であるがゆえに抱える課題について、動画や漫画、SNSなど市民に身近な様々な媒体を活用しながら、より一層の広報に取り組んでまいります。
押本:次に、県との協議等についてです。4月に黒岩知事が「特別自治市構想とは政令指定都市が県から独立し、県を分断するものです。」とした特別市構想の本質に誤解を与えかねないパンフレットを作成しました。これについて、市長は既に記者会見において大人の対応をするとの発言をされています。改めて見解と対応を伺います。
市長:次に、県が作成したチラシにつきましては、これまでの県の主張と何ら変わりはないものと考えておりますが、住民目線から見て特別市を法制化することは妥当ではないという県の見解は、これまで本市の市議会における決議や全町内会連合会から要望をいただいている中で、大変違和感を覚えているところでございます。今後の人口減少社会等への対応を見据えると強い危機感があり、今こそ我が国の地方自治の在り方を見直す時期に来ていると認識しております。市民の皆様によりよい行政サービスを提供し続けていくとともに、将来にわたって日本が成長、発展していくためには特別市制度が必要であると考えておりますので、引き続き、全国の指定都市とも連携を図り、法制化に向けて取組を進めてまいります。
押本:次に、地方自治法の一部改正案についてです。5月30日に衆議院本会議で可決されました。指定都市市長会からは、既に2月に、指定都市と国が直接、情報を共有し、迅速な対応ができるよう、指定都市の実情を踏まえ、運用面も含めた適切な制度設計を行っていただくよう、強く要望するとの緊急要請がなされています。法が予定する非平時の定義が曖昧な上、法の運用において指定都市が県の指揮命令下に置かれかねないなど、この間の地方分権の流れに逆行する懸念もあります。特別市構想を推進する視点から、法改正後の運用に対する見解と対策などについて、以上全て市長に伺います。
市長:地方自治法の一部改正案についての御質問でございますが、今回の改正の趣旨は、感染症の蔓延や大規模災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の特例として、機動的に国民の生命、身体等を保護できるようにすることにあると認識しております。こうした中、本年2月に示された改正案におきましては、指定都市に対する道府県の関与が残されており、人口、人流が集中する大都市圏域においては、改正の趣旨である機動的な対応に支障が出る懸念がございます。そのため、指定都市市長会として、指定都市と国が直接情報を共有し迅速な対応ができるよう、運用面も含めた適切な制度設計について国に要望したところでございますので、その動向を注視してまいります。
押本:次に、川崎市市制100周年記念事業について伺います。初めに、かわさき100フェスについてです、100と飛躍をかけて飛躍祭と銘打ち、川崎ゆかりのアーティストが集結し、等々力球場で初の音楽フェスティバルを実施するとのことです。このフェスに市民招待を募集したところ、10組20名の枠に対し、約1,600組からの応募があったとのことですが、区ごとの申込割合について伺います。今回のフェスの運営事業者は、チケットの売上げが今回の収入になる契約とのことです。フェスの周知広報については主に市が担っていますが、万が一、想定以上に余剰が生じた場合、本市に責任が及ぶことも懸念されます。見解を伺います。
総務企画局長:初めに、かわさき飛躍祭についての御質問でございますが、かわさき100フェスの市民招待では、全1,622組の応募者のうち中原区民が約35%を占め、以下、高津区18%、幸区13%、宮前区10%、多摩区9%、川崎区と麻生区が7%となっております。また、市及び実行委員会は、チケットの販売状況によって責任を負うことはございませんが、広報・PR面での取組を強化し、認知度向上やチケット販売促進を図ってまいります。
押本:次に、ブルーインパルスについてです。フェスでは、100周年を祝し、会場上空を飛行することが決定し、飛行時間に関する問合せが多く寄せられるなど市民の関心が高いことが分かります。飛行ルートについて防衛省との調整の結果、羽田飛行ルートに影響する南部は難しいものの、フェス会場の中原区以北にも飛行する計画とのことです。事前飛行も併せ、具体的に伺います。また、事前の周知は重要です。対象地域に対し、防災無線の活用や町内会・自治会掲示板へのポスターの掲載等、事前周知を早急に図るべきと考えますが、見解と対応を伺います。
総務企画局長:次に、ブルーインパルス展示飛行につきましては、かわさき100フェスとの一体的な演出で等々力緑地上空を飛行することが計画されており、前日の28日には予行飛行が予定されております。飛行ルート等につきましては、現在、防衛省において調整を進めている状況でございまして、決定次第、公式ウェブサイト等で公表してまいります。
押本:次に、食とスポーツが融合したイベント「アッと等々力フェス」についてです。地域経済を活性化させるよい機会と考えますが、フェスに参加する店舗の市内外及び種別について伺います。また、商店街連合会や経済労働局とはどのように連携を図ってきたのか伺います。さらに、このフェス以外にも年間を通し様々な地域でイベントが計画をされています。南北に細長い本市は、区同士の交流が少ない地域もあることから、こうした機会を活用し、食を通じた交流を図ることも有意義と考えます。見解と対応を伺います。
総務企画局長:次に、アッと等々力フェスにつきましては、出展する飲食関係店舗25店舗のうち、市内店舗は10店を予定しており、経済労働局からは店舗情報の提供を受けたところでございます。また、これまでも実行委員会参画団体の主催事業として食に関する取組が創出されており、市民の皆様に市内各所へ足を運んでいただくきっかけになっているものと考えております。引き続き、こうした取組を広く周知することにより、食を通じて他の区の魅力を知って、関わって、好きになっていただけるよう取組を進めてまいります。
押本:次に、内部統制全般について伺います。まず、個人情報の取扱いについてです。本市では、学校現場、庁内等において個人情報の紛失が相次いでおり、とりわけ5月27日に報道発表された、まちづくり局交通政策室のUSB紛失は深刻です。1,660件の個人情報が保存されていましたが、そもそもUSBメモリーの管理については、川崎市情報セキュリティ基準に基づき、情報管理責任者である業務所管課長が保管、管理しているはずです。今回はなぜ機能しなかったのか、原因と反省点及び今後の改善点を伺います。
本事案を受け、5月27日に総務企画局長名で、現物確認を含む管理状況の緊急点検を5月末までに実施する旨の要請をしていますが、結果について伺います。次に、個人情報を含む書類の紛失等についてです。これら事案が発生するたびに再発防止や注意喚起を求めていますが、一向に減りません。電子データ化のさらなる推進とともに、一目で分かるような視覚による書類識別手法などの対策も検討すべきと考えますが、見解と対応を伺います。
また、5月27日、川崎市立聾学校での就学奨励費関係書類の所在不明について報道発表されました。幼児、児童生徒数計41名に対し、5名分の書類が所在不明となりました。書類に記載されている個人情報は、口座情報のみならず、障害手帳や療育手帳の有無及び障害の等級等、極めて配慮を要する情報であり、ずさんな管理の実態が明らかとなりました。これまでも教育委員会事務局における個人情報の紛失事案は度々発生しています。教育長の所感及び原因と反省点、今後の改善策について明確に伺います。
総務企画局長:次に、個人情報の取扱いについての御質問でございますが、USBメモリーの管理につきましては、まちづくり局交通政策室で発生した個人情報を含むデータを格納したUSBメモリーの所在不明事案を受けまして、本年5月27日付で、情報セキュリティ責任者である各局区長に対し、各所属のUSBメモリー等の現物確認を含む管理状況の緊急点検を5月末までに実施するとともに、定期的な棚卸しや継続的な利用状況の管理を徹底するよう通知したところでございます。この緊急点検につきましては、各局区からの結果報告は求めておりませんが、今年度につきましても、毎年実施している情報資産の棚卸し及び局点検の結果を通して、各局区のUSBメモリーの実数確認を含む管理状況を確認してまいります。次に、個人情報を含む書類の紛失についてでございますが、本市の情報セキュリティ基準等では、個人情報が記載された書類は施錠可能な書庫等に保管することなどを規定しております。まずはこうした基本的な対策を徹底してまいります。また、各職場において実施している個人情報の取扱いやその管理方法等の好事例を収集し、研修等において紹介するなど、具体的な取組を迅速に進めてまいります。
まちづくり局長:初めに、USBメモリーの所在不明についての御質問でございますが、このたび、駐車施設附置届出書などの電子データを格納したUSBメモリーが所在不明となったことにより、市民の皆様に御迷惑と御心配をおかけいたしましたことをおわび申し上げます。USBメモリーの利用につきましては、川崎市情報セキュリティ基準に基づき、利用記録を作成し、貸出し返却を確実に行うこととされておりますが、このたびの事案は、管理職が不注意によりこれを怠っていたことが原因と考えておりますことから、職員への周知徹底が不十分であったことを反省点として捉え、情報セキュリティの重要性について十分理解するため、6月3日と4日に交通政策室において管理職を含む全職員に対し情報セキュリティ研修を実施したところでございまして、引き続き局内全職員への周知徹底を図ってまいります。今後の改善点につきましては、局内において管理しているUSBメモリーについて、必要最低限の保有数とした上で、管理体制を強化するため、局総務部門で一括管理してまいります。
押本:次に、多摩区役所における橋梁定期点検委託業務の落札取消しについてです。設計書作成の際、項目の選択を通常と異なった方法で入力し、誤った歩掛かりで積算した予定価格により入札が行われた結果、落札中止となる重大な設計ミスが発生しました。設計書の審査は二重、三重のチェックが行われており、本来であれば落札取消しは避けられたと考えますが、原因及び改善策を具体的に伺います。さらに、今回ミスのあった項目について、開札前に応札者から質問があったとのことです。改めて誤りを確認できる機会があったにもかかわらず、発見できずに見過ごしたことについて再発防止策を伺います。次に、今回の落札取消しという重大な結果を受けて、担当者だけでなく、審査者や係長、課長を含めた決裁権者の人事評価にどのように反映されるのか伺います。
多摩区長:橋梁定期点検業務委託についての御質問でございますが、初めに、落札決定取消しとなった原因及び改善策についてでございますが、担当者が設計するに当たり、本来、橋梁定期点検業務等積算基準の歩掛かりを使用すべきところ、確認不足により積算システム上で測量業務標準の歩掛かりを選択してしまったこと、さらに、審査担当者の思い込みによるチェック不足が原因でございます。こうしたことから、改善策として、積算に当たっての注意事項等、今回の事例に特化した研修を3月に道路公園センターで実施し、4月に建設緑政局による今回の事例を含めた研修を受講させたところでございます。次に、質問書への回答に関する再発防止策についてでございますが、質問を受けた際には、設計内容を再度確認し、正確に回答するよう今回の研修の中で職員に周知徹底したところでございます。取消しによる影響は決して軽易なものではないことから、今回の事案を重く受け止め、再発の防止に努めてまいります。次に、職員の人事評価についてでございますが、人事評価は年間を通じた職務の遂行状況等に応じて評価を行うものでございますので、今後につきましても、同様な事案が生じた場合には、その原因などを定められた評価基準に照らし、厳格に評価に反映してまいります。以上でございます。
押本:次に、川崎市総合計画改定に向けた基本的な考え方について伺います。5月29日の総務委員会にて新たな総合計画の方向性が示されました。初めに、現行計画の総括についてです。総合計画の構成は、これまでと同様に3層構造とのことです。議決案件である基本構想、基本計画については、現行の考え方を基本としながら、必要な見直しを行うとのことですが、どのような総括をいつまでに行うのか伺います。この部分につきましては他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。
押本:次に、改定に伴う市民からの意見聴取についてです。現行の総合計画が策定された際、かわさきの未来を考える市民フォーラムや、無作為抽出された市民から成る新たな川崎の未来を考える市民検討会など、多様な機会を設け市民意見の聴取を行ってきました。新たな総合計画を改定する際にはどのような手法を用いるのか伺います。次に、第4期実施計画の策定についてです。市民により分かりやすい計画とするため、実施計画の構成を抜本的に見直すとのことです。これまでの本市の総合計画の利点として、川崎再生フロンティアプランの時代から、他都市よりも綿密かつ情報量も豊富で、市職員の人材育成やスキルアップにも役立ってきた経緯があります。市民に分かりやすい計画とすることは賛同しますが、安易に単純化することは、市がこれまで培ってきた利点を失うことにつながりかねません。昨今、本市は民間コンサルタントに行政計画策定を依存しがちであることからも、新たな実施計画の策定に当たっては、市民と市職員の双方にとって好影響をもたらす作業方針となることを求めます。見解と対応を伺います。また、現在の実施計画では、施策の体系ごとに多くの成果指標が並んでいます。我が会派は、第1期実施計画から約10年にわたり、アウトプット型の成果指標からアウトカム型にシフトするよう求め、総務企画局とともに事業局に対し改善を促してきました。効果が発現していない成果指標や分かりづらい指標については削減するなど、見直しを図るべきと考えます。見解と対応を伺います。次に、収支フレームの考え方についてです。総合計画の推進に当たっては、収支フレームに沿った財政運営を行うことになっています。第3期実施計画は、コロナ禍における計画期間であったことから、中長期にわたる事業等に大きな影響が出ました。とりわけ投資的経費については、新規分、継続分、基礎的なものがありますが、新たな総合計画の事業推進に当たっての財政的な裏づけの考え方を伺います。この部分につきましては他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。
総務企画局長:次に、総合計画の改定についての御質問でございますが、市民からの意見聴取につきましては、このたびの改定では基本構想及び基本計画についても検討を行っていくことから、これまでの実施計画策定時に実施してきた市民説明会やパブリックコメント等に加え、無作為で抽出した市民によるワークショップでの議論も予定しており、夏以降の開催に向けて現在検討を行っているところでございます。次に、第4期実施計画についてでございますが、これまでの綿密な計画の策定業務等を通じて職員の政策形成能力の向上が図られるなど、人材育成に寄与する側面も見受けられる一方、機動性の面における課題等が顕在化しているところでございまして、市民にとって分かりやすく柔軟な運用が可能な計画となるよう検討を進めてまいります。なお、改定作業の基本的な考え方といたしまして、民間コンサルタントの活用は、将来人口推計に必要なデータ収集等、一部の業務に限定することとし、改定に向けた企画及び立案については、市長を本部長とする総合計画策定推進本部において推進するとともに、各局区の本部において所管事業等の検討を進めることで職員の主体的な参画を促進してまいります。次に、成果指標についてでございますが、これまで川崎市政策評価審査委員会からも専門的な視点等により様々な御意見をいただき、改善に取り組んできたところでございます。計画改定に当たりましては、一層の改善を進めていく必要があると認識しており、各局と連携しながら、適切かつ効果的な指標となるよう検討してまいりたいと考えております。
押本:また、令和4年3月に改定された今後の財政運営の基本的な考え方では、第4期実施計画期間中である令和10年度から、毎年20億円の減債基金の返済が予定されています。確実に実施されるのか見通しについて伺います。
総務企画局長:次に、行財政改革プログラムについての御質問でございますが、現在、行財政改革第3期プログラムに基づき3年目の取組を進めているところでございますが、いまだ効果の発現に至っていない取組があることに加え、社会経済環境の変化等に伴う新たな課題へも的確に対応していく必要があるものと認識しております。こうしたことから、総合計画の改定作業と緊密に連携しながら、さらなる経営資源の確保等を進め、持続可能な行財政基盤の構築とともに、より質の高い市民サービスの安定的な提供に向け、次期行財政改革プログラムの策定に取り組んでまいります。
押本:次に、新たな総合計画と次期行財政改革プログラムについてです。現在、第3期プログラムが実施中ですが、総合計画第4期実施計画と仮称行財政改革第4期プログラムはどのように整合性を図っていくのか伺います。
次に、新たな総合計画と区役所改革の基本方針についてです。現行の方針については、総合計画との整合性を図りながら、行財政改革プログラムを踏まえて目指すべき区役所像を明らかにするとしています。新たな総合計画の改定を踏まえ、区役所のデジタル化など社会変容が見込まれる中、新しい区役所改革の基本方針策定の考え方とスケジュールについて伺います。
また、これまで我が会派は、人、物、金、情報といった経営資源の確保や議論する場がないまま、本庁から区役所に業務移管されることに改善を求めてきました。局区間の調整については、区長連絡会議、副区長会議、区課題調整会議等、各種会議が重層的に存在していますが、本庁から区役所へ上意下達で政策を進めるのではなく、政策の意思決定に区役所が参画できる仕組みを考える必要があると考えます。見解と対応を担当の加藤副市長に伺います。
副市長:初めに、局区間の調整についての御質問でございますが、地域課題や市民ニーズが多様化、複雑化し、急激に変化する状況に適切に対応するためには、本庁事業局と市民に身近な区役所との意思疎通を図りながら政策形成を進めることが重要であると考えております。本市では、区における総合行政の推進に関する規則に基づき、区総合行政推進会議をはじめ、区役所と局との調整に係る会議等を設置し、協議調整に取り組んでいるところでございますが、その前提として適時適切な情報共有は大変重要だと考えておりますので、本庁各局と区役所がそれぞれの役割に応じて地域課題の解決に向けた取組が進められるよう、これらの仕組みを効果的に活用しながら、政策決定過程や事業推進における局区間調整のさらなる充実を図ってまいりたいと存じます。
押本:次に、出資法人への再就職全般について伺います。これまで我が会派は、出資法人の役割として、行政機能を補完、支援するとともに、昨今の公務員の人手不足や定年延長といった社会情勢の変化に対応することが重要であり、法人の組織体制の強化を繰り返し求めてきました。令和5年11月下旬の総務委員会では、例年、年度末に開催されている再就職選考委員会を秋頃に前倒しして開催するといった新たな取組の方向性が示されました。事前の調査では、公益財団法人川崎市文化財団から理事長職の求人があったとのことです。いきなり法人のトップ、企業でいえば社長の求人が出されており、当該法人の意思決定過程を示す会議や議事録等が見当たりません。所管部署と人事課はどのように確認をしたのか伺います。また、他の法人で同様のケースはないのか伺います。
次に、出資法人の経営改善及び連携・活用に関する指針では、人的関与の状況等に関する情報の透明性を確保し、広く市民に対する説明責任を果たすことが定められています。法人トップの求人を求める意思決定が法人内でブラックボックス化されていては、人事における公平性や妥当性が確保されているのか疑念が生じます。選考過程を明らかにし記録に残すなど、速やかに改善することを求めます。対応を伺います。また、法人トップを交代するに当たっては、本来であれば法人内で一定の役職を経験した後に就任するほうがマネジメントとしては自然と考えます。このことは、選考委員会の委員からも、トップがいきなり入替えというのは一般論ではどうなのか、下から上がるというのを原則にしていくのが大事ではないかという声が出ています。委員からの意見が反映されなかった理由を伺います。同じく摘録からは、選考委員会委員の見解として、公益財団法人川崎市国際交流協会の求人に対し、当該法人がTOEICや英検など語学資格保有者が望ましいとの要望を示しているにもかかわらず、本市は別の人材をマッチングしていることから、今後はきちんと語学力を尺度に入れた方がいいかと思うとの意見が付されています。このことからも、選考委員会委員は、適材適所の考え方の下、有益な意見を付しているにもかかわらず、総務企画局は前例踏襲的に退職職員をマッチングしているだけで、選考委員会の意見は全く反映されておらず、同委員会が形骸化しています。所管部署である人事課は、選考委員会委員の意見が反映される仕組みを速やかに構築すべきです。見解と対応を伺います。
総務企画局長:次に、出資法人等への再就職についての御質問でございますが、本市出資法人等が本市退職職員の採用を希望する場合は、雇用期間や役職、職務内容等を記載した求人情報登録申込書を本市に提出することとしており、当該申込書の提出の要否や求人内容については各法人内で決定されているものでございますので、意思決定過程の確認は行っておりません。次に、いわゆる法人のトップの求人についてでございますが、これまでも同様の事例はございまして、令和5年度におきましては川崎市文化財団のほか、かわさきファズ株式会社、川崎市消防防災指導公社、川崎市学校給食会などからございました。次に、求人に関する法人等の意思決定過程についてでございますが、法人内の手続の明確化を図るため、求人情報登録申込書の提出に当たって法人内の決裁を経ることなどについて、各法人に働きかけるよう所管局に促してまいります。次に、再就職候補者選考委員会での意見についてでございますが、選考委員会は、再就職に係る透明性等の確保とともに、法人が求める人材の情報と職員の知識、経験などを踏まえ、候補者の選考を行うものでございまして、各委員から様々な御意見をいただいた上で、最終的に委員会として候補者を決定し、当該求人に対して人材情報を提供しております。次に、選考委員会についてでございますが、各委員からの御意見は大変参考になるものであると考えておりますので、今後につきましても、いただいた意見を踏まえ、より求人内容に適した人材情報を選考委員会に諮れるよう取り組んでまいります。以上でございます。
押本:次に、ふるさと納税について伺います。初めに、現地決済型についてです。さきの予算審査特別委員会では、既に総務省の地場産品基準に適合し、本市に登録をされている返礼品の中からゴルフ場や宿泊施設等で導入するとの答弁でした。この間の進捗及び寄附実績について伺います。また、宿泊施設等への周知についても、拡大に向け、効果的な周知の手法等を検討の上、取り組むとしていましたが、その後の対応を伺います。
さらに、市長も4月2日の定例記者会見の中で、チャレンジングと前置きした上で、飲食という形にも拡大していく予定であり、ターゲットにしてしっかりやっていきたいと抱負を述べていますが、今後の展開及び業界団体への周知等について市長に伺います。
市長:ふるさと納税についての御質問でございますが、現地決済型ふるさと納税につきましては、本年4月から川崎国際生田緑地ゴルフ場で利用を開始し、一定の寄附をいただいているほか、宿泊施設におきましても導入が進んでいるところでございます。こうした中、飲食店もその対象に加えることにつきましては、寄附受入額の増加につながるものと認識しておりますので、利用可能な施設の拡大に向け、関係団体や事業者等に対しまして、あらゆる機会を捉え、現地決済型ふるさと納税の周知を進めてまいります。
押本:次に、ポータルサイトについてです。本市でも令和元年度からポータルサイトの利用を始めましたが、手数料の高さが課題となっています。そこで、ポータルサイトを通じた寄附受入額及び要した手数料について、年度ごとにそれぞれ伺います。次に、ガバメントクラウドファンディングについてです。初めに、税控除の仕組みについてです。そもそも市民は川崎市に寄附しても返礼品を受けられませんが、クラウドファンディングは市民も税控除が受けられるとのことです。仕組みについて詳細に伺います。次に、新たな取組についてです。昨年、神戸市は、NPO法人4団体に対するクラウドファンディングを実施し、全てで目標を大幅に上回る寄附金が集まりました。また、名古屋市は今年度から、NPO法人の実施事業に対し、ふるさと納税で支援できる仕組み、ふるさとNPOセレクトを創設しました。新たな取組により、寄附者は、より具体的なイメージを持って寄附が可能となり、NPO法人は、資金獲得に加え、告知のための情報発信の場が提供されることになります。本市でも、ふるさと納税を活用した支援の仕組みを創設することについて見解と対応を伺います。さらに、泉佐野市は、地元企業による地場産品の開発や品質向上等を支援できる「#ふるさと納税3.0」というクラウドファンディングを創設し、億単位の寄附金を集めています。導入自治体が増えていることから、本市でも導入を検討すべきと考えますが、見解と対応を伺います。
財政局長:初めに、財政運営についての御質問でございますが、減債基金借入金の返済につきましては、今後の財政運営の基本的な考え方におきまして、早期の返済を取組目標としておりますので、令和10年度からの返済が着実に実施されるよう、税源涵養や行財政改革に積極的に取り組むなど、効率的な財政運営に努めてまいります。
次に、ふるさと納税についての御質問でございますが、現地決済型ふるさと納税につきましては、本年4月から受付を開始したところでございまして、現在は川崎国際生田緑地ゴルフ場のほか、市内の宿泊施設でも導入が進んでおり、5月末時点での寄附受入額は249万円余となっております。次に、宿泊施設等への周知につきましては、川崎ホテル旅館組合を通じて周知を行うほか、個別に宿泊施設に伺い、現地決済型ふるさと納税への加盟を促すなど、利用可能施設の拡大に取り組んでいるところでございます。次に、ポータルサイトを通じた寄附受入額及び手数料につきましては、令和元年度は受入額4,015万円余、手数料43万円余、令和2年度は受入額1億3,189万円余、手数料312万円余、令和3年度は受入額3億5,138万円余、手数料2,199万円余、令和4年度は受入額5億8,790万円余、手数料5,060万円余でございます。次に、クラウドファンディングにおける税控除の仕組みにつきましては、クラウドファンディングを活用し本市へ寄附していただいた場合におきましても、確定申告などを行うことにより、地方税法上、ふるさと納税として寄附金税額控除の適用を受けることができるものでございます。次に、ふるさと納税を活用したNPO法人への支援につきましては、既存の寄附制度を含めた各種団体に関する制度との整合性の整理のほか、本市が団体に補助金を交付する際の公益的活動の範囲の精査や、団体間の公平性の確保などの課題もございますが、本市財源の拡大に資する取組となるかどうかも含めて検討してまいります。次に、ふるさと納税を活用した市内企業への支援につきましては、本市に立地している企業の特性等を踏まえながら、実現可能性を検討していく必要があることから、他都市の事例について研究してまいります。
押本:次に、定額減税及び調整給付に係る課題について伺います。令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税、県民税で定額減税等が実施されています。制度設計が複雑なことで、連日マスコミでも取り上げられています。また、1年限りにもかかわらず、本市だけでもシステム改修費として約7,500万円、コールセンター等給付業務で約4億8,500万円を要する事業であり、本市での事務分担は財政局、健康福祉局がそれぞれ担いますが、対応するための組織体制について伺います。また、コールセンターの人員体制も具体的に伺います。次に、定額減税において、定額減税し切れないと見込まれる方に給付金が給付されます。本市の対象者数見込みについて伺います。また、申請しなければ給付を受けられませんが、非常に複雑な制度のため、理解を促す周知は大変重要です。市民への周知は市政だよりやホームページを活用するとのことですが、理解促進の工夫及び発行する時期について伺います。さらに、コールセンター以外に市税事務所や区役所など窓口に直接問合せが寄せられることも想定されます。マニュアルや想定問答集の準備等、どのような対応を検討しているのか、人員配置や問合せ先の周知方法と併せて具体的に伺います。対象者は令和5年度実績による推計所得税額で算定されます。国からの算定ツールが5月末に送られてきたとのことですが、これに係る運用上の課題について伺います。また、推計所得税額で算定しているため、調整給付額に過不足が生じる可能性がありますが、対応について伺います。本事業では、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外になりますが、見込まれる対象者数についても伺います。
財政局長:次に、定額減税及び調整給付についての御質問でございますが、組織体制でございますが、財政局におきましては、定額減税に関する事務のほか、調整給付の対象者の抽出及び給付額の算定を行っており、このうち調整給付に関して、課長級を含めた4名体制で対応しているところでございます。また、健康福祉局におきましては、対象者への給付に係る事務を行っており、課長級を含めた4名体制で対応しているところでございます。次に、コールセンターの人員体制につきましては、各給付金事業全体で月ごとに想定される問合せ件数に応じて、最大28人のオペレーターを配置しております。次に、調整給付の対象者数でございますが、現時点におきましては約27万人を見込んでおります。次に、給付金の広報につきましては、確認書等の送付時期に合わせて、市政だよりの7月号に調整給付以外の給付金も含めた制度の概要や手続方法等について掲載を予定しているほか、市ホームページにおきましても各給付金の具体的な手続方法等に関する情報を順次掲載してまいります。次に、問合せにつきましては、専用のコールセンターで対応しておりますので、電話番号やメールアドレスを市ホームページや対象者に送付する各種書類に掲載するなど、広く周知してまいります。なお、窓口に直接来庁された方への対応につきましては、市税事務所職員向けの研修を実施したほか、窓口設置用のチラシや想定問答集を作成するなどの事前準備を行い、適切に実施しているところでございます。さらに、9月末まで区役所及び支所に相談員を各2名ずつ配置し、手続等を御案内しているところでございます。次に、推計所得税額の算定ツールにつきましては、個人住民税の課税資料から推計額を算出しており、また、寄附金控除や住宅ローン控除なども反映されない仕様となっていることから、推計所得税額と確定後の所得税額が大きく異なる場合があることが課題となっております。次に、過不足が生じた場合の対応につきましては、制度上、過大に給付を行っていた場合には返還を求めず、給付額に不足が生じた場合には、令和7年度に不足分を追加で給付することとなっております。次に、合計所得金額が1,805万円を超え、定額減税の対象外となる方につきましては、約1万2,000人を見込んでいるところでございます。以上でございます。
押本:次に、川崎市プレミアムデジタル商品券事業についてです。初めに、関係団体への意見聴取についてです。過去の川崎じもと応援券事業では、関係団体との意見聴取の機会が設けられなかった事例があり、丁寧な意見聴取と制度設計への反映についてただしてきましたが、今回の事業構築に当たり、寄せられた意見及び見解と対応を伺います。
次に、事業者選定についてです。さきの定例会における代表質疑では、幅広い市民の利用促進と利便性向上のため、一部の決済事業者だけでなく複数の電子マネー決済が望ましいと指摘しました。今回、1事業者となり、商業者からは、当該決済システムの加入、未加入や、1事業者のみに税金を投入することに疑問の声も寄せられています。1事業者となった経緯について具体的に伺います。この部分につきましては他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。
また、こうした懸念に対する見解と対応について伺います。あわせて、キャッシュレス決済が不慣れな方への対応策についても伺います。次に、中小企業等での利用促進策についてです。商店街をはじめ中小企業等での利用促進策を求めてきましたが、見解と対応を伺います。また、中小企業等へのキャッシュレス決済導入へのフォローについて伺います。
財政局長:初めに、プレミアムデジタル商品券事業についての御質問でございますが、関係団体への意見聴取につきましては、事業実施に当たり、商業者等のニーズを把握することは重要であると考えておりますことから、商業団体と事前に意見交換を行いまして、プレミアム分を市内だけで使えるようにすべきである等の御意見をいただき、制度設計の参考とさせていただいたところでございます。事業者の選定に当たりましては、4者から提案があり、今回選定した委託事業者からの提案が最も多くの市民の皆様の利用機会を確保できるものと考えており、本事業のキャッシュレス決済サービスのメリットを市民の皆様にお伝えし、利用促進を図るとともに、より多くの店舗に御参加いただけるよう様々な機会を通じて御案内してまいります。キャッシュレス決済サービスの不慣れな方への対応策につきましては、利用者向けのコールセンターを開設し、スマートフォンの操作方法等の御案内を6月3日から開始したほか、6区役所とかわさき きたテラス、セレサモスをはじめ、かわさき飛躍祭等のイベント会場において日時を定めてサポートブースを開設するとともに、市内のスマートフォン一部販売店舗でも操作方法等に不慣れな方への対応を実施するなど適切にフォローしてまいります。中小企業等への対応につきましては、商店街をはじめとした店舗での利用拡大が必要であると考えておりますことから、本事業の商品券の利用店舗であることを示す案内ポスターやのぼり旗等の配付、商店街等からの希望に応じたサポートブースの設置など、利用促進に向けた支援を行ってまいります。中小企業等へのキャッシュレス決済サービスの導入に向けたフォローにつきましては、未導入店舗への専用コールセンターの設置をはじめ、委託事業者による商店街等への訪問サポートを実施しているところでございます。
押本:次に、川崎市中央卸売市場北部市場の更新計画について伺います。初めに、さきの定例会における質疑で、市場の生鮮品の経由率について、令和5年度中に取りまとめるとの答弁でした。その結果を伺います。次に、令和5年度の青果物、水産物、花卉それぞれの取扱量の実績額を伺います。次に、市場使用料についてです。事業収支シミュレーションでは、62年間の総事業費1,450億円のうち、1,002億円を市場使用料で充てており、さらに整備費等が増加した場合には、市場使用料の増額等により収支を合わせることを基本とするとの答弁でしたが、基幹収入である市場使用料は場内事業者の経営動向に大きく左右されます。既に更新後の市場使用料を2倍程度にすることで収支均衡が図られるとの見込みも示されていますが、この負担増に対応できるのか大いに懸念するところです。5月30日と31日で場内事業者に対し、要求水準書に関する説明を終えたと仄聞しますが、市場使用料を2倍に引き上げることについて、場内事業者の合意が取れたと理解するのか、また課題があれば伺います。また、市場使用料の値上げ幅を抑制するため、市場更新整備の諸所の具体的なダウンサイジング案を提案し、検討を強く求めたところです。検討結果について具体的に伺います。さらに、昨年度末に老舗の水産仲卸業者が突如営業を停止し、現在、破産手続が進められています。場内事業者が不在の北部市場更新計画はあり得ません。今後、62年間にわたって事業継続の意思があるのか、市場使用料を支払い続けることが可能であるのかなど、場内事業者の意思確認を具体的に行う必要があると考えますが、見解と対応を伺います。
財政局長:次に、北部市場の機能更新についての御質問でございますが、北部市場における青果物及び水産物の経由率につきましては、令和4年度の市内販売割合は、青果物が18.5%、水産物が38.3%でございます。また、令和5年度の取扱数量につきましては、青果物が約8万9,255トン、水産物が約1万6,639トン、花卉が約2,986万本でございます。市場使用料につきましては、収支均衡を図る上で基幹的な収入であることから、適正に確保することが求められており、場内事業者に使用料の上昇について十分な説明を行う中で、場内事業者からは、急激な負担増に対する不安などの御意見もいただいておりますので、今後の事業費の変動及び場内事業者の経営状況等も踏まえながら、場内事業者の事業継続が図られるよう、使用料の設定について慎重に整理してまいります。市場使用料の抑制につきましては、事業者との協議を進める中で、市場使用料に影響を与える全体の整備費を抑えるため、例えば、仲卸売場などの内装設備等の整備を最小化し、場内事業者が必要に応じた設備導入をすることで費用を削減するなど、整備区分の見直しを進めてきたところでございます。場内事業者の意思確認につきましては、再整備後の安定的な市場運営に向けて重要なことと認識しておりますことから、基本計画の策定の段階において、算定した売場面積を確実に借り受けることについて場内事業者に確認しておりますが、今後、基本設計や実施設計などに向けて、個々の事業者の業務の継続意向を引き続き確認してまいります。
次に、神奈川県川崎競馬組合の移転について伺います。5月31日、昨年3月末に閉鎖された神奈川大学湘南ひらつかキャンパス跡地の売却先として、同組合が優先交渉権事業者になったことが明らかになりました。同組合は、狭小化や老朽化が課題であった川崎競馬小向厩舎と練習馬場の移転を検討しており、今回の応募に踏み切ったと報じられています。事実経過について具体的に伺います。また、本市への説明状況についても伺います。次に、同キャンパスの敷地面積は約31ヘクタールであり、厩舎地区を整備する余裕はないものの、馬場や坂路といった必要不可欠な施設は配置できる見通しと報道されています。厩舎や練習馬場全体の移転が検討されているのか伺います。さらに、今回、優先交渉権事業者として選定されただけであり、移転が決定したわけではない旨の説明があったとのことですが、移転した場合の本市への影響についてどのように想定しているのか、以上、担当の加藤副市長に伺います。
副市長:次に、川崎競馬小向厩舎等の移転についての御質問でございますが、川崎競馬小向厩舎及び練習馬場につきましては、狭く過密な環境、建物の老朽化等の課題が顕在化していることや、令和元年東日本台風の際に大きな被害を受けたことから、神奈川県川崎競馬組合において、県内あるいは県外にある複数の候補地への移転について検討が行われてきたところでございます。そうした中、同組合が県内候補地の一つとしておりました神奈川大学湘南ひらつかキャンパス跡地の売却に向けた公募が本年2月から始まり、同組合が検討したところ、厩舎地区として必要不可欠な施設が配置できる見通しが立ち、公募という手法のため、優先交渉権事業者として選定されなければ土地を取得できないことから、この機会を逃さずに公募に参加することになったと伺っております。その後、学校法人神奈川大学による選定の結果、5月31日に同組合が優先交渉権事業者となったものでございます。本市への説明状況につきましては、同組合から構成団体である本市に対して、検討状況や公募への参加などについて必要な情報提供が適宜ございました。また、移転施設等につきましては、厩舎及び練習馬場で検討が進められているものでございます。同組合は優先交渉権事業者となり、同大学と交渉を進めていくことになりますが、移転となった場合の本市への影響につきましては、小向厩舎及び練習馬場の移転は本市としても大きな課題と認識しておりますので、今後とも状況を注視してまいりたいと存じます。以上でございます。
押本:次に、障害福祉サービス事業所に対する勧告及び指定についてです。まず、障害者グループホーム事業者「恵」への処分についてです。さきの定例会における代表質問では、最終的な事実確認を行い、本市の処分量定に基づき厳正に実施してまいりますとの答弁でしたが、その後の経過を伺います。また、給付費の不正受給及び食材費の過大徴収についての処分量定と、不正受給分の返還スケジュールを伺います。次に、障害者施設・事業所の処分量定について、国に対して統一した基準の作成について要望するとの答弁でしたが、その後の取組と経過を具体的に伺います。次に、我が会派が提案した市内グループホーム116事業所を対象とした食材費徴収の実態調査の結果、不適切な事案が疑われる回答もあり、今後、調査内容をまとめ、調査を追加して内容の確認を行う旨の答弁でしたが、その後の経過を伺います。あわせて、未回答の事業者への対応を伺います。次に、高津区に新設された障害者生活拠点施設「ナーシングピア子母口」に対する勧告についてです。市有地を無償で貸与し、本市からの施設整備費約9億円の補助を受け、昨年11月に開所しましたが、市から事業の指定を受けたにもかかわらず、開設当初から所定の人員配置を怠り、一部の事業が開始できず、さらに不正受給も行っていた実態が明らかになりました。なぜ2月まで本市として課題を認識できなかったのか伺います。また、5月8日に勧告をし、7月31日までに改善状況の報告を受ける予定です。本市の想定される処分の量定を伺います。さらに、審査結果の評価項目では、強い意欲と積極的な姿勢が感じられることに大きく加点されていましたが、審査議事録によると、選定法人は高齢者施設が主であり、障害者施設の運営については懸念を指摘する声もありました。そうした指摘があったにもかかわらずモニタリングにつながらなかったのか、見解及び具体的な課題点について伺います。
健康福祉局長:初めに、障害者グループホーム事業者「恵」についての御質問でございますが、令和4年7月から監査を実施し、厚生労働省とも連携を図りながら調査を行ってきたところでございまして、令和6年第1回川崎市議会定例会以降につきましては、本市が確認した不適切な事項等について、事業者に対し事実確認を行った上で、行政手続法に基づく弁明の機会の付与を行い、当該事業者への処分について令和6年6月7日付で決定したところでございます。処分量定につきましては、監査結果において、給付費の不正請求のほか、人格尊重義務違反等の事実が認められたため、令和6年7月1日から令和6年12月31日までの6か月間の指定の全部の効力停止処分としたところでございます。また、不正受給分の40%の加算金を加えた約1,290万円の返還スケジュールにつきましては、近日中に返還期日を定めて、改めて当該事業者に対し通知を行う予定でございます。統一した処分量定基準を国が示すことの要望につきましては、適宜本市の要望を伝えているところでございまして、引き続き厚生労働省に対して要望をしてまいります。食材料費の徴収に係る実態調査につきましては、食材料費として徴収した金額と支出した金額の差異がある事業所が相当数あり、差異の内容などにより不適切な事案が疑われる事業所を絞り込むための精査に時間を要しております。精査後、指導監査が必要となる事業所を特定し、実態の把握に向け、スピード感を持って追加調査を実施するところでございます。あわせて、まだ回答のない事業所に対しましては、引き続き電話等による督促を行うほか、必要に応じて現地調査を行い、できるだけ早く未回答事業所の実態の把握に努めてまいります。
押本:次に、社会福祉法人母子育成会の不正について伺います。5月30日に健康福祉局から報道発表された事案です。まず、議会への情報提供についてです。当該法人の自主調査により、法人内において不正な会計処理がなされていた疑いが判明したため、令和5年10月27日から同年12月まで監査を実施したとのことです。監査の実施からおよそ7か月も経過していますが、議会への報告に時間を要した理由を伺います。
健康福祉局長:次に、障害福祉サービス事業所に対する勧告についての御質問でございますが、障害福祉サービス事業所の運営状況等の確認につきましては、通常、障害福祉サービスの質の確保及び給付の適正化を図ることを目的に実地指導を実施し、確認をしているところでございますが、利用者の増加に伴い事業所数が年々増加していることから、指導監査について時間を要しているところでございます。対象となった事業所につきましては、日中サービス支援型のグループホームのため、制度上、年に1回以上の協議会等による評価を受けるとともに、協議会等からの必要な要望、助言を聴く機会を設けることが定められていることから、本市における川崎市地域自立支援協議会での評価に向け、令和6年2月に本市が当該事業所の運営状況等を確認したところ、改善が必要な状況を把握したものでございます。処分量定につきましては、改善が必要な事項に対し指導等を行ったところでございますので、引き続き、その改善状況に応じて、必要な措置を含めた対応をしてまいります。拠点型施設の開設後の運営状況等の確認につきましては、運営法人による他県での障害者施設の運営実績を確認していることや、事業所開設に向けた様々な調整、指定申請に係る相談、申請受理後の現地調査など様々な機会で連携を図るため、運営に支障を来す事態があった場合にすぐに相談に乗れるような状況をつくっておりましたが、一方で、現地での状況確認を行う機会が不足していたため、不適正な状況の把握ができなかったものと考えております。こうしたことから、今後につきましては、本市にとって重要な役割を果たす拠点型施設の運営状況等について適時確認を行う体制の強化や、選定時に法人に対し具体的な人員配置等の計画を求めるなどの検討が必要であると考えております。
押本:また、今年度の当初予算では、法人が運営をする乳児保育園「夜間保育所あいいく」の大規模修繕整備事業費として約2億5,600万円が計上されています。不正な会計処理が横行していた当時の理事長が解任及び告訴されるといった法人の不祥事について、これまで健康福祉局及びこども未来局から情報提供がなかったため、我々議会は、さきの定例会において、その事実を知らぬまま予算認定するに至っています。当局は、既に監査において法人の不正会計に係る事実を把握し、本年3月に文書指導していたにもかかわらず、議会への情報提供が遅れた結果、税金が不正を働いていた法人へ議会質疑なく流出したことを重く受け止めるべきです。当局の情報提供のタイミングや議会対応は改めるべきと考えます。反省点と今後の対応を担当の三田村副市長に伺います。
副市長:母子育成会の監査結果についての御質問でございますが、本件につきましては、新たな役員体制が発足し、前理事長による不正が行われている可能性があるとの報告を受けた中で、健康福祉局に対し、法人運営状況の正確な把握とそれに伴う監査の実施を指示するとともに、利用者や家族等へのサービス提供が継続されるよう指示してまいりました。今回の事案につきましては、今年度の予算審査と監査が同時期に進行しており、監査結果が確定していなかったため、議会への情報提供はできなかったところでございます。今後、万が一こうした事案が発生した場合につきましても適切に対応してまいりたいと存じます。以上でございます。
押本:次に、当局による監査状況についてです。事前のヒアリング調査では、平成28年の時点で、当局が、法人の経営状況が厳しいことや、本年3月、不正会計を確認したとして文書指導を行ったとのことでした。法人が長年不正会計を働いていたことからも、過去の監査で発見できなかったのかという問いに対し、担当職員からは、口約束で監査を済ませていた、信頼関係で済ませていたという、にわかに信じられない当局のずさんな監査体制が明らかになり、後日の新聞報道でも同様の内容がありました。事実関係について改めて伺います。
また、当該法人の過去の役員構成等を確認したところ、本市のOBが関係者として複数在籍していたことから、監査のなれ合いが強く推察されます。これまでの監査がずさんであった原因と反省点及び今後の改善策について、市長及び健康福祉局長にそれぞれ伺います。
市長:母子育成会の監査結果についての御質問でございますが、過去の本市の監査に際して、前理事長が財務書類の改ざんや領収書等の挙証資料を不正に準備していたと報告を受けております。公益性が求められる社会福祉法人制度に反する行為であり、本市所管の法人でそのような行為があったことは大変遺憾なことと認識しております。同法人の監査を数年にわたって実施してきた中、経営が悪化していること、会計処理の不備はこれまでも指摘してまいりましたが、実際に不正を発見するまでに至らなかったことは課題であり、反省しなければならないと認識しており、今後の指導監査に生かしてまいります。
健康福祉局長:次に、今回の監査結果の公表に至る経過でございますが、平成28年度に神奈川県から監査の権限が移管された時点で、経営状況に課題があるということの引継ぎを受けており、その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い法人から監査辞退の申出があった令和2年度、令和3年度を除き、毎年指導監査をしている中で、経営が悪化していることや会計処理の不備を把握し、指摘をしておりました。他方、前理事長は、不正が極力見つからないように、他社の押印済みの領収書つづりを入手する、実態のない取引の領収書の作成を取引先に依頼するなど、巧妙に隠蔽や改ざん行為を行っており、その結果、監査において全体像の把握に至らず、費用の未計上や債務の計上漏れの指摘等にとどまり、前理事長による個人不正の把握にまでは至りませんでした。令和5年3月に新たな役員体制が発足し、前理事長による不正が行われている可能性があるとの相談を受け、法人運営の状況の正確な把握とそれに伴う監査の実施を行う中で今回の事態が発覚したところでございます。本市の監査につきましては、これまで国の定めるガイドラインに基づき実施してまいりました。なお、法の規定及び厚生労働省から、所轄庁は犯罪捜査のための立入検査を行う権限は有していないとの指導を受けていることから、本市の監査では捜査権限は有しておりません。一方で、今後につきましては、今回の事案を踏まえ、法人とのより深い対話や議論を通じて実態把握に努め、法人運営の適正化につながる監査指導となるように取り組んでまいります。次に、母子育成会の監査結果についての御質問でございますが、母子育成会につきましては、令和5年3月に新たに業務執行理事に就任した現理事長が法人状況を確認したところ、不自然な経理処理の疑いがあることについて同年4月に相談があり、改めて同年6月に本市に報告がございました。本市においては、法人からの報告を受け、法人の財務報告体制の実態を把握するため、既に予定していた令和5年度の法人監査スケジュールを組み直し、会計専門家を通常の監査よりも増強するなど、監査を行う体制の調整を行ってまいりました。監査体制が整った令和5年10月27日から12月18日まで監査を行い、その後、専門的な知見を用いた調査、指摘等を踏まえて、令和6年3月26日付で監査結果通知を発出し、法人からの改善報告を同年4月30日に受領したところでございます。監査後も、事案の重大性を鑑み、利用者への影響を軽減し、安心・安全なサービス提供が継続されることを重視したことにより、同年5月30日の公表となりました。
押本:次に、法人のガバナンスについてです。一般的に社会福祉法人には監事が法に基づき設置されますが、この間、どのように機能していたのか伺います。また、当局は、過去の監査において、法人の経営状況が厳しい状況であったことを確認していましたが、法人の監事が正しく機能していたのか、どのようにチェックしてきたのか伺います。さらに、前理事長が解任、告訴され、法人運営のガバナンスは刷新されたとのことですが、現在はどのように改善されたのか具体的に伺います。次に、当該法人に対する財政的関与についてです。法人は複数の特別養護老人ホームや保育園を経営していることから、本市から多額の介護給付費や委託料が支払われています。毎年どの程度支出しているのか伺います。当局の報道発表資料には、前理事長による法人資産の私的流用や不正行為は枚挙にいとまがないと記載され、その後の報道では、少なくとも約8億5,000万円以上の私的流用があったとのことですが、本市が受けた損害はどの程度なのか、この質問については他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。
健康福祉局長:次に、社会福祉法人における監事についてでございますが、社会福祉法により法人には、理事の職務の執行を監査するため、監事を2名以上設置する必要があることが規定されており、当該法人において監事による監査報告書が作成されていること、理事会、評議員会の議事録において議論した形跡がないことを本市の監査において確認しております。こうしたことから、監事等の役割が十分に機能していなかったものと捉えております。なお、過去も含め、監事へのヒアリングは実施しておりません。現在の法人の運営体制についてでございますが、かつては理事長しか知り得なかった金銭の動きや会計処理について、令和5年3月に新たに就任した理事、監事や評議員及び会計担当者を含め各事業所の管理者、事務員とも連携を図り、透明性の高い法人運営を進めているとの報告を受けており、今後も継続的に確認を行ってまいります。次に、本市から法人に対する支出についてでございますが、主な支出は介護給付費、保育給付費、補助金、委託費等、合わせて約20億円になります。以上でございます。
押本:次に、こども誰でも通園制度について伺います。さきの定例会における代表質問では、保育・幼児教育関係の団体等に対し、概要説明及び意見聴取を始めたとの答弁でした。聴取した意見と、事業内容や要綱への反映について伺います。先日の文教委員会にて、定員数が本市の想定より少ないとの報告でしたが、想定に対する充足率について伺います。また、年度途中で通常の保育定員が充足した場合、本制度は継続できません。現時点で想定より低い中、どのように対応するのか伺います。次に、受入れに関するリスク低減のため、預かる前に事業者の面談が必須ですが、利用者が殺到した場合、事業者に過大な負担がかかることは避けられません。適切な面談を迅速に行えるサポートや相談窓口の明確な周知など、本市の支援が不可欠と考えますが、見解と対応を伺います。次に、国のアンケート調査結果では、保育者から、地域の子育て支援の意義は認めるものの、半数以上が、事務仕事や時間、労力が増え負担を感じる、通常保育に比べて子どもが環境に慣れることが難しいなど、労働環境の負担が明らかです。対応について伺います。次に、こども家庭庁は本制度の意義として、孤立した育児家庭への支援やハイリスクの子どもへのアプローチ等を示しています。名古屋市ではアウトリーチで支援が必要な方の利用を確保する取組を行っています。本市の見解を伺います。また、支援が必要な子どもがいた場合の保健師や区との連携について伺います。
子ども未来局長:初めに、こども誰でも通園制度仮称の本格実施を見据えた試行的事業についての御質問でございますが、本事業における各種団体への意見聴取の結果につきましては、月10時間の利用上限がある中で、どの程度のニーズがあるのか不透明であることや、補助金額が低いことなど、主に国の制度設計に関する懸念や不安などの御意見を確認いたしました。また、複数の施設や自治体をまたぐ利用時間の管理は難しいとの御意見もありましたので、同時期に利用登録できる施設を子ども1人につき1施設に限定するとともに、利用対象者も市内在住者に限定する取扱いとし、要綱に反映したところでございます。次に、定員の充足率につきましては、国への応募に際して計画した必要定員数764人に対し、実施施設の受入れ定員数は合計で195人のため、定員充足率は約25.5%となっております。通常保育の受入れ状況によっては、年度途中で受入れを停止せざるを得ない施設があることも想定されますが、本市の課題として検証し、結果を国に報告してまいりたいと存じます。次に、実施事業者に対する本市の支援についてでございますが、現在、安全に受入れができるよう、公立保育所において面談の際に健康状態や受入れに当たっての配慮事項等を聞き取るための様式を作成し、提供することを予定しております。また、相談窓口といたしましては、施設所管課がそれぞれ対応するほか、各区の保育・子育て総合支援センターや保育総合支援担当の職員が適宜巡回し、保育技術に関するアドバイスや相談対応を行う予定でございますので、実施事業者が必要な相談支援を受けられるよう適切に周知を図ってまいります。
次に、令和5年度の預かりモデル事業における保育者へのアンケート調査の結果において、保育に慣れていない児童を預かること等による保育者の業務負担等について示されているところであり、課題の一つとして認識しているところでございます。今年度の試行的事業においても、本格実施を見据えた、より明確な実施条件の下、実施施設の創意工夫による最適な実施方法の検討と併せて、国は運営上の課題についても引き続き検討することとしておりますので、本市においても、今後、本事業を実施する中で、保育者の負担を含め、様々な課題に対してしっかりと検証を行い、国に報告するとともに、本格実施に向けた必要な対応について要請を行ってまいります。次に、本事業につきましては、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化することを目的としていることから、利用促進を図ることで、より支援が必要な家庭を適切に関係機関につなげていくことが重要と考えております。次に、保健師との連携につきましては、保育所等では、これまで虐待等の疑いがある緊急ケースや発達に課題のある子ども等への対応について、保健師と連携しながら対応しており、本事業におきましても同様の対応が必要と考えております。
押本:次に、全国都市緑化かわさきフェアについて伺います。秋の祭典は約4か月後に迫ってきましたが、いまだ周知が十分とは言えない状況です。さきの定例会における質問に対し、参加を通じて興味や関心を持っていただき、継続的な活動につなげていくことが重要と考える旨、答弁されています。子どもや高校生、周辺企業等との取組は実施しているものの、長年にわたり緑の保全活動に取り組んでこられた複数の団体にヒアリングしたところ、いまだにアプローチも協力要請も全くないとのことです。緑の保全団体は、高齢化の進捗により活動の縮小や解散を余儀なくされているところも少なくなく、緑化フェアとのコラボレーションによる活動のPRは、新たな担い手発掘の好機と考えます。緑の保全団体との協働・連携について今後どのように取り組むのか、本市が描くレガシーの考え方と併せ、対応を具体的に伺います。
次に、マスコットについてです。本市では、基本計画策定時からマスコットはつくらない方針だったとのことですが、そのように決断した理由について、理念と併せ明確に伺います。あわせて、既存マスコット「森の妖精モリオン」の利活用について伺う予定でしたが、他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。
次に、交通アクセスの課題についてです。本市のコア会場は、いずれも駅から遠く、交通アクセスは集客や回遊性に影響すると考えます。令和5年6月のまちづくり委員会で我が会派の委員が、会場が分散していることから、富士見と等々力、等々力と生田間をシャトルバスなどで結ぶことを提案しました。それに対し担当課長は、緑化フェア幹事会の中で、等々力と富士見を結ぶほうがよい、観光と組み合わせてもいいという意見をいただいており、引き続き検討を進めたい旨、答弁しています。その後の検討状況を具体的に伺います。次に、横断歩道上の点字ブロックについてです。我が会派は、これまでも設置を求め、今回の100周年記念事業等に合わせて、駅からコア会場へ続く動線上の横断歩道上への整備も求め続けてきました。県からの情報では、令和6年度予算で川崎駅周辺の市役所通りと新川通り11か所の横断歩道上に設置されることが決まったとのことです。横断歩道上の点字ブロック設置は県の権限とのことですが、他の区での設置について、県との調整状況を伺います。次に、新たな情報インフラについてです。羽田空港や金沢市などでは、新たな案内機能として多言語にも対応可能なコード化点字ブロックを設置しています。これは点字ブロックにマークを付加してコード化し、スマートフォンをかざすことで情報が提供されるものです。既設の点字ブロックにも施工でき、情報量は1枚で1億2,000万種類が登録可能であることから、各コア会場や最寄り駅、主要駅構内などに設置することで、緑化フェア来場者の利便性向上や会場内外の情報提供が可能になり、相乗効果が期待できると考えますが、見解と対応を伺います。
建設緑生局長:初めに、全国都市緑化かわさきフェアについての御質問でございますが、かわさきフェアにおいては、これまでの市民協働の取組を大切にしながら、地域の団体と未来のまちづくりを担う子どもたちや若者が出会い、新たなつながりを生み出していくとともに、企業、地域の団体等を巻き込み、フェア開催以降も継続できる新たな協働、共創による仕組みの構築につなげていくこととしております。そうした中で、保全された緑地における活動に取り組む団体とのフェアを通じた協働等につきましては、団体の方々と取組を紹介する展示やワークショップ等の実施を通じて情報発信や参加の呼びかけを行い、保全活動等に関わるきっかけづくりに取り組んでまいります。次に、会場へのアクセスにつきましては、交通輸送の基本的な考え方として、昨年8月に策定した基本・実施計画では、公共交通機関の利用を前提としながら、来場者には最寄り駅から会場まで、徒歩を中心に緑を感じ、歩いて楽しめるルートの案内や、駅周辺の商店街などの地域資源を楽しんでもらえる案内を掲げており、この考え方に基づき取組を進めていることから、各会場間を結ぶバスについては運行しないこととしております。なお、これまでに観光などのコンテンツとの組合せについての御意見もあったことを踏まえ、旅行会社等が企画する会場間をつなぐバスツアーなどについて、バスの運転手確保の課題なども鑑みながら、現在、調整を行っているところでございます。
次に、エスコートゾーンにつきましては、本市では、川崎駅東口駅前広場から川崎市視覚障害者情報文化センターに向かう経路上にある日進町交差点など、川崎区において4か所の設置事例がございます。その他の区につきましては、現在のところ設置事例はございませんが、エスコートゾーンは視覚障害者が横断歩道を歩行する際の安全性や利便性を向上させるために有効であると認識しておりますので、今後、他の区での設置につきましても、交通管理者に事業推進を求めてまいりたいと考えております。次に、コード化点字ブロックにつきましては、視覚障害者への歩行支援以外にも、観光客等への情報提供にも利用されている事例もございますことから、かわさきフェアでの活用につきましても、事業者や施設管理者等と協議調整を行いながら検討してまいります。
押本:次に、生田緑地ビジョンについて伺います。初めに、ナラ枯れについてです。生田緑地では、被害本数は累計で1,914本に上りますが、伐採本数は560本にとどまっています。環境への影響や生物多様性を保全する観点から、迅速で適切な対応が求められますが、当局は、今年度末に示すアクションプランで植生管理計画の見直しについて検討を進めるとのことです。今後の対応策については、ロードマップを作成し試算もしているとのことですが、財源の考え方と併せ具体的に伺います。次に、回遊性の向上についてです。緑地内には様々な木道があり、散策を楽しむ園路となっていますが、ナラ枯れの影響でいまだ5割ほど通行止めになっています。老朽化により安全対策が必要な箇所もあり、緑化フェアの開催前に修繕、整備すべきと考えますが、見解と対応を伺います。次に、居心地がよく誰もが快適に過ごせる空間の在り方についてです。ビジョン改定に向けた視点の整理として示された新たな価値創出や社会課題解決のための場となるには、インクルーシブへの対応が挙げられています。利用者アンケートでも、居心地がよい場所づくりや園路のバリアフリー化、遊具や子ども遊び場設置等の意見が寄せられています。そこで、広く生田緑地の周知につながり、あらゆる人が様々な形で楽しめる居場所となる手法として、インクルーシブ遊具の設置が有効と考えますが、見解と対応を伺います。計画では、今年度中に仮称生田緑地ビジョンアクションプランを取りまとめるとしています。具体的な取組が示されることから、途中経過について議会に報告すべきと考えますが、見解と対応を伺います。
建設緑生局長:次に、生田緑地ビジョンについての御質問でございますが、ナラ枯れにつきましては、昨年度までに緑地内の主要なエリアをつなぐ園路について処理を行い、動線を確保したところで、残る被害木のうちの半数につきましては、園路や施設に影響がなく、今後処理を必要とする樹木は約600本でございます。令和6年度につきましては、3,900万円の予算を一般財源として計上し、約80本の伐採を予定しておりまして、引き続き市民が通行する園路を優先的に対応していくところでございます。また、植生管理計画につきましては、今年度策定を予定している仮称生田緑地ビジョンアクションプランの中に計画の見直しを位置づけて取組を進めてまいります。次に、全国都市緑化かわさきフェアに合わせた生田緑地の回遊性の確保につきましては、フェア開催に支障がないよう、会場運営に必要となる園路について、優先的にナラ枯れ対策や木道の補修等を実施しているところでございます。次に、インクルーシブにつきましては、ビジョンでは、居心地がよく誰もが快適に過ごせる空間の創出等を目指しておりますことから、遊具の設置も含め、インクルーシブな空間づくりについて検討してまいります。次に、アクションプランの策定に当たりましては、様々な方々との情報共有や意見聴取が重要と考えており、適宜議会へも報告を行うなど、引き続き取り組んでまいります。
押本:次に、五反田川放水路整備事業及び関連事業について伺います。令和4年2月に、多摩川水系平瀬川ブロック河川整備計画の策定に伴う氾濫解析により浸水想定面積が変更されましたが、議会がその報告を受けたのは令和6年3月になります。遅れた理由が効果的な対策を検討していたためとしていますが、定例会や常任委員会等、説明の機会があったにもかかわらず正確な報告がなされなかったことは、紛れもなく瑕疵と指摘せざるを得ません。また、この2年以上、議会からの質問に対し行われた答弁と整合性が図られていたのか伺います。次に、この事業では、長年にわたって地元住民を中心とした二ヶ領本川等治水対策協議会等が組織され、準備が進められてきました。念願の放水路が完成し、大幅に浸水想定面積が減少したものの、三沢川流域等も含めた新たな整備事業が生じる結果となりました。住民に対し丁寧な説明と協力が必要ですが、見解と対応を伺います。
建設緑生局長:次に、五反田川放水路整備事業等についての御質問でございますが、初めに、議会への報告につきましては、令和4年2月に多摩川水系平瀬川ブロック河川整備計画が策定されたことから、改めて五反田川放水路整備後の効果を検証した結果、浸水想定面積が変更になったことに加え、新たに二ヶ領本川下流部の追加対策が必要となることが判明したものでございます。その後、現地調査や測量を行い、対策案の抽出に時間を要したことから、市議会へは本年3月の報告となったものでございまして、報告までに時間を要し、申し訳ございませんでした。この間、議会からは、浸水想定面積に係る御指摘はございませんでしたが、当初の計画との整合性を図りながら、事業効果の早期発現に向け取り組んできたところでございます。次に、住民への説明につきましては、本年5月に、二ヶ領本川等治水対策協議会において現状と今後の対応について説明したところでございまして、今後、令和元年東日本台風で被害を受けた地域住民の皆様へも丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。
押本:次に、防災・減災対策全般について伺います。初めに、能登半島地震の支援についてです。本市は、3月18日から31日まで、応急仮設住宅建設に係る業務支援として3名を現地に派遣しましたが、課題や得た知見について伺います。あわせて、本市の防災施策等にどのように生かしていくのか伺います。
危機管理監:災害時支援物資受援体制についての御質問でございますが、初めに、能登半島地震における課題認識につきましては、本市が担当した避難所は物資拠点も兼ねており、物資の搬出入等の作業は避難所運営職員で対応し、物資の搬入規模、時間、内容について事前連絡がなかったため、搬入後の仕分けや在庫管理に多くの時間を要するなど、物資拠点における災害時物流の課題を改めて認識したところでございます。また、本市における対応につきましては、物資を円滑に避難者に届けるため、国、関係機関と支援物資や道路啓開に係る情報共有を行うこと、アクセス性、機能性の高い物流施設や輸送力を有する民間事業者と連携を推進すること、さらに、今後、石川県などが作成する検証報告も参考としながら、引き続き災害時支援物資受援体制の実効性の確保に努めてまいります。
押本:次に、災害時支援物資受援体制の構築についてです。能登半島地震では、発災当初、避難者へ物資を振り分ける作業の担い手確保や、支援物資集積拠点から避難所までの確実な供給及び輸送ルートの確保、各避難所のニーズ把握、情報収集方法など、多くの課題が浮き彫りとなりました。さきの定例会における代表質問では、派遣職員の感想として、避難所の物資について、在庫があるものがプッシュ型で送られ、整理に時間を費やしたとの答弁でした。教訓とした課題認識とその後の本市対応について伺います。また、我が会派はこれまでも、円滑かつ迅速な供給体制を構築するため、民間施設を含め新たな物資拠点の在り方やアンケートの実施、受援マニュアルの策定、地域防災計画の改定、訓練の実施など早急な取組を促すとともに、議会への報告を求めてきました。その結果、昨年6月の総務委員会にて進捗が報告され、その資料において、現状残された主な課題も抽出されたところです。資料によると、市職員の対応力や関係機関との連携体制構築、市内部の役割分担等の整理、調整、物資拠点候補施設の実効性の確保検討、周辺自治体及び民間事業者等との連携、陸上輸送以外の手段検討が挙げられていますが、改善状況及び今回の課題認識や本市対策の検討を踏まえた今後の取組を伺います。
次に、令和元年東日本台風による浸水被害への対策についてです。昨年9月、我が会派が令和元年東日本台風の発災以前より取組を求めてきた山王排水樋管周辺地域におけるバイパス管の運用開始等についての住民説明会が開催されました。その際の資料では、既に実施済みである短期対策の効果や中長期対策の進捗状況などが示されましたが、特に長期対策の取組については、その内容等に変更はなく、住民に対して根本的な解決策への将来展望を示すには至っていません。この長期対策として、山王排水樋管においては、新設雨水幹線の延伸や丸子ポンプ場の増設用地確保など、分流地区の4つの排水樋管では、流下幹線の新設や統合ポンプ場の用地確保、新設など、段階的な整備による効果の発現も期待されます。段階を追った具体的なスケジュールを示すことが肝要ですが、いつまでに行うのか伺います。また、それら取組や検討内容及び整備計画の変更、更新等についての見解と対応を伺います。
危機管理監:次に、災害時支援物資受援体制の在り方及びマニュアルにおける課題につきましては、マニュアル策定後の取組として、職員を対象とした研修会の開催、機能性の高い施設を有する民間事業者との協定締結の推進、県、協定事業者、拠点候補施設と連携した実地訓練の実施、トラックの待機スペースや資機材の保有状況の確認など優先順位の高い施設に対する現地調査、周辺自治体との支援物資受援に係る情報共有などを行ってまいりました。本年1月4日に急遽実施した氷見市への飲料水提供に際しても、これらの取組に基づき、関係局区、協定事業者が連携し、支援決定の当日に物資を現地までお届けするなど、迅速な対応を行ったところでございます。今後の取組につきましては、民間事業者との施設の使用に関する調整を踏まえ、庁内における役割の分担の調整や、海上輸送や航空輸送に係る国の動向、能登半島地震を踏まえた職員研修や訓練内容の見直し、民間事業者との災害時協定のさらなる推進などについても取り組んでまいります。以上でございます。
押本:次に、水道料金制度等の在り方の検討について伺います。4月の環境委員会において水道料金制度等の在り方検討の報告があり、料金制度の見直し等の課題解決に向け、経営審議委員会へ諮問する計画が示されました。初めに、現行の料金制度については、昭和44年度に改定されて以来、これまで見直しが行われませんでしたが、この間、経営審議委員会等から制度改定への提言が行われなかったのか伺います。また、その後の水道料金改定の経緯について伺います。次に、多量使用事業者からの水道料金収入が、平成22年度約56億円から令和4年度約33億円と大きく減っていますが、その理由について伺います。次に、財政シミュレーションでは、令和4年3月の中期計画策定時と比較して、純利益が大きく乖離していくことが示されています。とりわけ下水道事業会計では、物価上昇の影響が128%となっています。具体的要因と削減に向けた今後の取組について伺います。関連して、5月28日の環境委員会において、県内5水道事業者による施設整備計画の策定についての報告がありました。この計画の実施に伴う本市水道事業の負担見込額について伺います。また、神奈川県内広域水道企業団からの受水費など、本市水道事業への影響をどのように評価しているのか伺います。
上下水道事業管理者:初めに、排水樋管周辺地域における長期対策についての御質問でございますが、長期対策のスケジュールについてでございますが、現在進めている概略設計に基づく取組内容について、事業費や関係機関との調整状況を踏まえ、次年度に策定する次期上下水道事業中期計画の中でお示ししてまいりたいと考えております。次に、長期対策の取組についてでございますが、長期対策の実現には大規模な用地確保が必要となることに加え、多大な費用と期間を要することなどから、対策施設の段階的な整備については、早い段階から効果が期待できる有効な手法であるものと認識しております。こうしたことから、概略設計の中で、先行整備する施設による効果の確認や下水道事業計画の変更方法など、引き続き長期対策の検討を深めてまいります。
次に、水道料金制度等の在り方の検討についての御質問でございますが、初めに、本市水道料金制度につきましては、昭和44年6月の料金改定において逓増料金制を採用して以降、計6度の料金改定を実施し、単価の改定等は行ってきているものの、制度の大枠は変わっていない状況でございます。平成7年度の料金改定における川崎市専門委員からの答申では、将来的な口径別料金体系への移行について、また、平成22年度の料金改定における川崎市水道事業経営問題協議会からの答申においても、基本水量制の廃止や口径別料金体系への移行などについて提言されておりますが、生活用水への配慮を念頭に、実施時期については十分な検討が必要とされているところでございます。次に、多量使用者の料金収入の減少要因につきましては、平成22年度と令和4年度の施設栓数及び調定水量を比較いたしますと、施設栓数は23%減少し、調定水量は42%減少しており、1栓当たりの調定水量は25%減少していることから、件数の減少と1件当たりの使用水量が共に減少していることが主な要因と考えられます。次に、下水道事業会計の財政シミュレーションにつきましては、主に電気料金の高騰に伴う動力費の増額により純利益が大きく減少しているものでございます。今後の取組といたしましては、令和5年度下半期から電力の契約形態を見直すことで動力費の削減を図っているところでございますが、その他の費用につきましても、今後の厳しい財政状況を踏まえ、引き続き削減に向けた検討を行ってまいります。
次に、県内5事業者による施設整備計画についての御質問でございますが、初めに、計画実施に向けた施設整備の費用につきましては、これまでの水源開発に係る事業と同様に、責任水量制、統一料金制を原則とする受水費により負担するものでございまして、具体的な施設整備費用及び負担時期につきましては、今後、県内5事業者で協議調整してまいります。次に、本市水道事業への影響につきましては、受水費の上昇は本市水道料金の上昇にもつながることから、県内5事業者での協議において、受水費が適正なものとなるよう努めてまいります。以上でございます。
押本:次に、2024年問題への対応状況について伺います。時間外労働時間の上限規制について、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から既に実施されており、建設業や運送業、医師については、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、適用は5年間猶予されてきました。本年4月に猶予期間が終わり、これらの分野でもいよいよ本格適用となったところです。初めに、川崎市立3病院についてです。さきの定例会における質問に対し、令和4年度に年間の時間外労働時間が960時間を超えた医師は、川崎病院で60名、井田病院で2名いたことから、各病院で委員会を組織し、川崎病院については特例水準の指定を受ける等、取組を進めるとの答弁でした。既に2か月が経過しましたが、この間の状況と取組について伺います。
次に、交通局についてです。この間、時間外勤務の実態等について、労働基準監督署から度々是正勧告を受けてきましたが、その内容と対応状況について具体的に伺います。次に、本年4月の本格適用に当たり準備を進めてきたとのことですが、条例定数の充足状況について伺います。次に、5月28日の環境委員会で、2024年問題に対応するため、6月10日から、平日95便、土曜25便、休日24便を減便するとの報告がありました。4月以降は時間外労働、休日労働、拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間等が規制されていますが、この間、基準を遵守できていたのか具体的に伺います。また、労働基準監督署の監督指導への対応状況について伺います。バス運転手の確保が厳しい状況は、既に数年前から指摘されています。そうした中にあっても必要なバス運転手を確保し、減便せずに運行を続けているバス事業者もある中、なぜ本市ではこうした状況に至ったのか、原因について伺います。本来確保すべき職員を確保できなかった結果、市民サービスの削減に至ったことは前代未聞と言わざるを得ません。こうした結果を招いた責任の所在について明確にお答えください。次に、減便は、朝のラッシュ時間帯は極力避け、運行本数が多く、運行間隔が短い路線から選定したとのことです。対象となる便で、いわゆる積み残しはなかったのか、また、減便により直後の便で積み残しが発生する可能性をどう分析、評価したのか伺います。次に、減便による収入減をどのように見込んでいるのか伺います。次に、バス運転手の早急な確保が必須です。これまでの施策では不十分であることが明らかになったと考えますが、今後の取組を具体的に伺います。また、待遇面を含め、抜本的な運転手確保策を行っているバス事業者もありますが、本市の見解を伺います。さらに、目標とする期限について伺います。
交通局長:初めに、労働基準監督署の是正勧告についての御質問でございますが、平成26年12月には交通局の本庁及び塩浜、井田、鷲ヶ峰の各営業所に対して、平成29年5月及び令和2年7月には塩浜営業所に対して、法令や労使協定を超える時間外勤務や休日勤務について是正勧告を受けております。勧告内容への対応といたしましては、事務職員の時間外・休日勤務について、事前手続や従事内容の確認の徹底、業務の見直しによる縮減や平準化を図るとともに、運転手につきましては、勤務計画の見直しなどにより適切な勤務体制の確保に努めてきたところでございます。次に、職員の配置状況についての御質問でございますが、本年4月1日現在の事務・技術職員、整備職員、運転手を合計した正規職員の定数は462名でございまして、実人員は435名でございます。なお、運転手につきましては、正規職員及び会計年度任用職員等の合計で342名在籍しており、安定的な運行を確保するための人数に対し、塩浜営業所及び鷲ヶ峰営業所の合計で14名の不足となっております。
次に、改善基準告示についての御質問でございますが、今般の改正におきましては、運転手の拘束時間、休息期間などについて規制が強化されておりまして、鷲ヶ峰営業所において基準に合致しない状況が生じた運転手の人数は、4月が78名、5月が65名でございます。また、労働基準監督署からの監督指導につきましては、令和3年度以降はございません。次に、鷲ヶ峰営業所管内における減便についての御質問でございますが、市バスでは、この間、勤務ローテーションの見直しなどの運行上の工夫や職員採用の取組強化を行い、運転手の確保に努めてまいりました。しかしながら、採用人数が予定数に達しなかったことなどから運転手が不足し、減便は避けられないものと交通事業管理者である私が最終的な判断をしたものでございます。対象となる路線では、日頃から多くのお客様に御利用いただいておりまして、時間帯によっては後発のバスを御利用いただく状況もあるものと承知しております。また、減便後におきましては、次発のバスだけではなく、それ以降のバスを御利用いただく場合や、他の時間帯のバスを御利用いただくケースもあるものと考えております。このたびの減便による収入への影響につきましては、後発のバスを御利用いただけるものと想定し見込んでおりませんが、今後の利用動向を注視してまいります。市バスを御利用のお客様には、混雑の発生や御乗車までの待ち時間、利用時間の変更などにより御不便、御迷惑をおかけするものと考えておりまして、大変申し訳なく思っております。
運転手の確保に向けましては、試験科目の見直しや日数の短縮、同一年度内における複数回の選考実施、採用時期の前倒し等について検討を行ってまいります。このたびは、運転手不足が生じている状況に早期に対応するため、一部の路線で減便を行いましたが、引き続き養成枠採用を含む運転手の確保に向けた取組を進め、その状況等も踏まえ、今後、ダイヤ改正を行ってまいります。以上でございます。
押本:次に、消防署所の整備・維持管理の考え方について伺います。4月の健康福祉委員会の報告では、老朽化が顕著な施設や感染症対策、個室仮眠室がないなど機能不足の施設について、今後の整備の方向性が示されました。6月末に稼働予定の宮崎出張所の次は子母口出張所の整備を予定しているものの、その後は、築年数が29年以上の22施設も含め未定との答弁でした。資産マネジメント第3期実施方針を所管する総務企画局と調整した上で同考え方を策定したとのことですが、全体の施設整備スケジュールが未定では予算確保のための説得材料が乏しく、危機管理施設である消防署所の整備計画としては不十分です。24時間稼働の危機管理施設である消防署所を他の公共施設と同様に捉えることは適切ではありません。全体の整備スケジュールを勘案した上で、時点修正を加えるべきと考えます。改めて関係局と調整した上で、同考え方の再検討を求めます。見解と対応を伺います。また、整備すべき22施設については、2年に1か所整備したとしても40年以上かかります。過去には2か所同時に整備していたこともあることから、再検討に当たっては同時並行で整備することも考慮すべきです。見解と対応を伺います。
消防局長:消防署所の整備・維持管理の考え方等についての御質問でございますが、初めに、本考え方は、これからの消防署所に求められる機能、救急需要等の分析に基づく施設配置の考え方等を整理し、本市に必要な消防力の確保を行うことを目的として策定したものでございます。高津消防署子母口出張所以降の整備対象施設につきましては、現在、施設劣化調査が完了している3出張所に加え、築40年以上が経過した川崎消防署小田出張所、中原消防署苅宿出張所及び井田出張所、高津消防署久地出張所の施設劣化調査を実施するとともに、各施設における必要機能の不足状況や、救急隊の新たな配置による波及効果を含む消防・救急需要の変化の検証等を行った上で、優先順位づけを見直し可視化してまいります。次に、整備につきましては、消防署所を現在地にて改築する際には、その施設の消防隊や救急隊は一時的に隣接の消防署所等へ仮移転する必要がございますことから、現在は必要な消防力を確保するために仮移転する消防署所が複数発生しないこととしているところでございます。しかしながら、今後は同時期に更新時期を迎える消防署所も想定されまして、スピード感を持って整備を進めることが重要であると考えておりますので、必要な消防力の確保に向けて、引き続き関係局と調整してまいります。以上でございます。
押本:次に、教職員勤務実態調査及び教員不足の状況について伺います。令和6年4月時点で未充足が131.5人と昨年より倍増となりました。このような深刻な事態を招いたことについて、教育長の見解を伺います。今年度の応募状況は、昨年度と比較しても応募倍率が下がっており、特に小学校については1.7倍となっています。これまで応募倍率が2倍を下回ったのは初めてであり、さらに厳しい状況であると考えます。見解及び評価について、教育長に伺います。また、追加の応募者確保のための早急な取組が必須と考えます。見解と対応を教育長に伺います。
教育長:次に、教員不足等についての御質問でございますが、教員不足につきましては、年度当初における教員の未充足数が昨年度より大幅に増加するなど、児童生徒への影響、教員の負荷などを踏まえますと、学校現場は厳しい状況にあるものと深刻に受け止めており、私が先頭に立って、教員不足の解消に向けた取組を推進していかなければならないと改めて認識しているところでございます。本市においては、児童生徒数が増加する中、募集人数を増やす取組の必要性が高いことから、さらなる応募者の確保を図るために、受験機会の拡充に向けた取組を検討し、可能な限り速やかに環境を整え、順次実施するとともに、今後、人材確保策の強化、働く環境の改善、業務改善の3つの取組の好循環を生み出す、より実効的な対応策を検討、実施してまいります。以上でございます。
押本:次に、教員不足解消に向けての取組についてです。まず、令和5年度から大学3年生を対象とした大学推薦による特別選考を導入しています。200校の大学に案内を送付し、29大学39名の学生の応募があったとのことです。令和5年第3回定例会における代表質問で大学との連携について質問し、周知の時期と方法、大学推薦枠の在り方等が課題であると認識しており、次年度に向けては、他都市も含めた今年度の試験実施状況を踏まえて、効果的な実施方法について検討するとの答弁でした。その後の検討状況について伺います。また、特別選考の合格者を確実に採用するための希望者に対する研修を行うとの答弁でした。その後の検討状況を具体的に伺います。次に、今年度新たに、近畿地方を対象に一次選考試験会場を設けるとのことです。地方受験者拡大のため、他都市のように二次試験等で必要な旅費や宿泊費を補助することについて見解と対応を伺います。また、令和5年度に本市の採用試験に合格し、名簿登載された合格者のうち、小学校の採用を辞退した者の数は60人、辞退率は23.8%とのことです。その中には地方受験者が地元を選択したケースも少なくないと仄聞します。千葉県と千葉市は、今年度から導入した奨学金返済全額肩代わり制度が教員志望者から大きな関心を集めています。本市の教職に就くためのインセンティブ及び辞退者を減らす取組として大変有効と考えますが、見解と対応を伺います。
次に、現在、児童生徒の増加に対応することを条件として一般任期付教員採用選考が実施されており、今年度は64人が採用となったということです。制度開始4年目となりますが、この制度利用者で既に正規教員となった実績について伺います。また、課題抽出や制度改善に向けて制度利用者の動向調査等もすべきと考えますが、見解と対応を伺います。この採用者の正規教員への定着をどのように図るのか具体的に伺います。次に、佐賀県等で実施されている年度内の複数回の採用選考も実施すべきと考えますが、見解と対応を伺います。次に、人材育成と人事配置による中学校教員の活用についてです。まず、中学校の倍率が高い教科は、小学校への異動も視野に多めに採用し、中学校からの異動による小学校での専科教員の配置を行っています。さらに積極的に進めることで教員不足に効果があると考えますが、見解と対応を伺います。さらに、教育の質の向上のために、中学校教員等の小学校教員免許取得の勧奨を目的に補助を行っています。担任不足対策として積極的に活用すべきと考えますが、見解と対応を伺います。
教育次長:初めに、教員不足についての御質問でございますが、大学3年次在籍者推薦につきましては、昨年度の実施状況を踏まえ、大学や学生へのさらなる周知期間を設けるため、案内の送付時期を10日程度早めるとともに、1校当たりの人数制限を2人から4人に拡大するなどの充実を図っております。また、希望者への研修につきましては、本市の教育の特色や学校見学などをテーマとした全7回の研修を計画し、これまで5回実施したところでございます。次に、奨学金の返還支援をはじめとした教員採用試験の受験者や採用者に対する支援につきましては、人材確保や人材支援の在り方についての検討を進める中で、他都市における取組状況や効果等について調査研究し、できる限り速やかにその方向性を取りまとめてまいります。次に、一般任期付教員の動向につきましては、令和4年度、令和5年度に採用した106人のうち、本市正規教員となった者は51人、引き続き一般任期付教員として勤務する者は46人、退職した者は9人となっており、一般任期付教員の採用は人材確保に一定程度寄与しているものと考えております。また、一般任期付教員につきましては、臨時的任用教員等の経験者とは異なり、経験年数によらず、教員採用試験の特別選考Ⅱの対象にするとともに、指導主事等による研修を行うなど、教員としての資質向上に向けた支援を進めているところでございます。次に、複数回の採用試験の実施につきましては、今年度、秋選考を行う自治体を参考に、本市におきましても、その実施に向けて試験の方法や時期等について検討しているところでございます。次に、中学校教員の小学校での活用についてでございますが、小学校専科教員の配置につきましては、専門的指導による授業の質の向上のほか、担任の負担軽減や教員不足への対応など様々な効果が期待されることから、引き続き小学校専科教員の公募等に取り組んでまいります。また、公募で小学校専科教員として配置された中学校教員で、小学校の免許状を取得した教員を小学校担任として活用することにつきましては、本人の意向やモチベーションを考慮しながら、効果的な人材育成や配置の在り方について検討してまいりたいと考えております。
押本:次に、学校施設の入札不調及び入札中止について伺います。材料単価や労務単価といった建築コストの高騰等の影響を受け、入札不調となったケースがある一方で、直近では、坂戸小学校校舎等増築事業や高津小学校給食室等増築工事では、関係局による連携不足、まちづくり局施設整備部における事務ミス等により巨額の公金損失が生じています。まず、入札不調対策についてです。これまで我が会派は、公共建築物整備の専門組織であるまちづくり局施設整備部の技能向上のため、職員の資格取得費用の一部助成や計画的な人材育成の着手、材料単価の見直し等、具体的に提案してきました。まちづくり局では入札不調対策に向け、どのような取組に着手しているのか伺います。
まちづくり局長:次に、入札不調及び積算ミスについての御質問でございますが、初めに、入札不調への対策につきましては、おととしまで年1回の見直しであった標準単価について、本年8月から年4回の見直しとするなど、より実勢価格に即した予定価格となるよう対応するとともに、今後も国や他都市の動向を注視し、関係局とも連携しながら、さらなる入札不調対策について検討してまいります。次に、積算ミスへの対策についてでございますが、人材育成の取組として、積算研修や勉強会等により職員のスキルアップを図るとともに、職員からの意見抽出などにより研修内容を向上させながら、チェック体制の確保につなげてまいりたいと考えております。また、これまでチェックリストの活用や、施設整備部内の複数人で工事内訳書の確認を行うなどの対応をしてまいりましたが、新たな取組として民間提案制度を活用した積算チェックシステムの実証実験を行うなど、多様な手法によりチェック機能の強化を図ってまいります。次に、教育委員会事務局との連携についてでございますが、学校施設の整備の遅れは、児童生徒や保護者、地域の方々に与える影響が大きいものであり、事務ミス防止のために職員同士のコミュニケーションを図ることは大変重要なことと認識しておりますことから、受託局として責任を持ってチェック体制を整えるとともに、教育委員会事務局とさらなる情報共有の場を設けてまいりたいと考えております。以上でございます。
押本:次に、人為的ミスによる入札中止についてです。人為的ミスによる巨額の公金損失及び工事遅延に伴い学校関係者に多大な影響が生じています。5月上旬に報告された高津小学校給食室等増築工事の入札中止では、まちづくり局の事務ミスにより工期が遅れ、その結果、事務費が5,000万円増加し、総額9億9,000万円になるとのことです。事前の聞き取り調査では、この事務ミスにより処分となった職員はいないとのことです。昨年、学校プールの事案で、教育委員会事務局は過失のあった職員等に対し、損害額の半額に当たる約95万円を弁済するよう求めましたが、市長事務部局の事務ミスで生じた5,000万円の公金損失に対し処分が不問になっていることは、職責に対する緊張感が欠如するとともに、局によって処分が異なるダブルスタンダードになりかねません。処分することが目的ではありませんが、一定の緊張感ある人事評価を求めます。今回の事務ミスによる反省点と対応を担当の藤倉副市長に伺います。次に、チェック体制の確保についてです。人為的ミスは必ず生じるものであり、その後のバックアップ体制を強化することが必要であると繰り返し指摘してきました。とりわけ積算ミスに起因することが多いことから、他都市の事例を参考にするなど、多様な手法を検討すべきと考えますが、具体的に伺います。また、まちづくり局施設整備部内でチェック体制が構築できないのであれば、事業執行に当たり、教育委員会事務局にまちづくり局出身の職員が存在することから、兼務した上でダブルチェックを行うなど協力体制を築くことも必要と考えます。見解と対応を伺います。
副市長:積算ミス防止に向けた取組についての御質問でございますが、入札中止による工事の遅れや事業費の増加などは市民生活に与える影響が大変大きいことから、工事の設計・積算業務に細心の注意を払って取り組むべきでありながら、行政のプロフェッショナルの技術職員として度重なるミスを生じさせてしまったことを深くおわび申し上げます。今回の入札中止により工期の遅れやさらなる費用負担が生じるなど、市民や関係者に与えた影響の重大性について重く受け止め、継続して予防的措置を講じることに加え、職員一人一人が緊張感を持ち、組織として具体的かつ実効性のある新たな再発防止策を講じるよう改めて指示したところであり、今後、その状況を確認してまいります。次に、職員の処分等につきましては、今回の事案が与えた影響の大きさとその背景に鑑み、管理監督者に対し厳正に対処するとともに、人事評価につきましては、制度の趣旨を踏まえ適切に対応するよう指示してまいります。以上でございます。
押本:関連して、公立学校施設費国庫負担金の在り方についてです。建築コストの高騰等による学校施設の入札不調が増加していることから、事業年度が変更した場合の国庫補助の再計上に当たっては、柔軟な対応を国に求めるべきであると指摘してきました。本市特有の課題でもありますが、関係局からは前向きに取り組むとの報告がありましたが、その後の対応について詳細を伺います。
次に、議案第94号、川崎市川崎市民館・労働会館条例の制定について伺います。初めに、再編整備についてです。我が会派は、これまでの総括の必要性とその検証スケジュールを明確にするよう求めてきましたが、見解と対応を伺います。次に、施設利用に関する規則や要綱等の制定と利用マニュアルの作成についてです。4月の文教委員会では、教育文化会館、労働会館の減免措置や事前申請は、これまでの各館の取扱いを基本に検討するとの報告でした。規則等の作成においては、利用団体、住民など、幅広い丁寧な意見交換、意見聴取が必要と考えますが、見解と対応を伺います。次に、危機管理についてです。当該施設の指定管理者は、分館を含め3施設を同時に運営することとなります。災害時の対応について具体的に伺います。また、災害時における各施設の役割や連携等を明確にすべきと考えますが、見解と対応を伺います。次に、指定管理引継ぎの課題についてです。我が会派は、引継ぎに関しては、十分な期間と、その間に発生をする運営準備費の設定が寡占化する事業者募集の改善に寄与すると提言してきました。見解と対応について伺います。
教育次長:次に、公立学校施設費国庫負担金についての御質問でございますが、国庫負担金の活用に当たりましては、国が認めた国庫補助の実施年度内に完了する工事契約を締結することが要件となりますが、昨今の急激な物価高騰や労務単価の上昇、災害復旧工事等による需給逼迫等に伴う資材不足や人材不足といった事情により入札不調が生じており、補助要件を充足することができないことがございます。そのため、こうした場合においても、国庫補助の再計上に係る柔軟な対応について、令和7年度国の予算編成に対する要請書に新たに要請事項として加えたところであり、今後、国に対して要請してまいります。
押本:次に、議案第103号、川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第104号、川崎市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について伺います。まず、応募状況等についてです。今回、中原・高津市民館及び橘分館、高津図書館橘分館の指定管理者募集が行われました。現地見学会・説明会の参加事業者数を伺います。また、1者選定にならないための応募事業者数を増やす取組を伺います。次に、指定管理の仕様等についてです。令和5年第4回定例会の我が会派の質疑において、専門性を維持しながら安定的に事業を継続できるよう、引継ぎ期間の費用の指定管理料への反映を検討するとの答弁でしたが、具体的な対応を伺います。次に、仕様書には最適な人材を配置するとの記載がありますが、具体的な基準がなく、教育委員会事務局民間活用事業者選定評価委員会でどのように評価するのか、具体的に伺います、また、我が会派が求めていた専門性の維持に関して、有資格者の配置条件等とその理由を伺います。あわせて、施設管理における市内事業者の積極的な活用等を検討するとのことでしたが、対応を伺います。
教育次長:次に、市民館条例及び市立図書館条例の一部改正についての御質問でございますが、初めに、現地見学会・説明会の参加事業者数につきましては、中原市民館では24事業者、高津市民館では22事業者、橘分館では20事業者となっております。また、より多くの事業者に興味関心を持っていただけるよう、昨年11月に川崎市PPPプラットフォームを実施し、事業者からの意見を参考に仕様書や募集要項を作成するとともに、公募期間を十分に確保することなどにより、多くの事業者が参入しやすい環境づくりに努めてまいりました。次に、引継ぎに伴う費用につきましては、他施設の状況や事業者へのヒアリング等を踏まえ、指定管理料の範囲内で実施する仕様としたところでございます。次に、人員配置につきましては、組織図や職員配置計画等の資料を提出していただき、必要に応じて事業者からの提案の比較資料を作成するなど、教育委員会事務局民間活用事業者選定評価委員会において総合的に評価してまいります。また、有資格者につきましては、市民館では各館1名以上の社会教育主事有資格者を、図書館では50%以上の司書有資格者を配置することで、それぞれ専門性を確保してまいります。次に、市内事業者の活用につきましては、業務の一部を第三者に委託する場合には、市内中小企業者を優先して活用する仕様としたところでございます。次に、社会教育振興事業につきましては、これまでの事業経緯や取組内容等について市から指定管理者へ引継ぎを行うとともに、それぞれの事業ごとに区の生涯学習支援部門と指定管理者の役割を明確化したマニュアルを作成し、指定管理者と共有するとともに、両者で定期的に打合せ等を行うなど連携して取り組んでまいります。
押本:次に、区の生涯学習支援部門についてです。まず、社会教育振興事業について、指定管理者は、区の生涯学習支援部門と役割分担し、連携して実施するとのことですが、仕様書には明確な記述がありません。引継ぎも含め、スムーズな連携への対応を具体的に伺います。次に、令和5年9月定例会の我が会派の質疑で、区の生涯学習支援部門の新たな役割、職務内容として、身近な場所での学びの場づくりや地域人材のさらなる活用に向けた取組を進め、区全域における社会教育振興や地域づくりを担うとの答弁でしたが、具体的な取組状況を伺います。また、指定管理者制度導入に伴う行政の体制や事業実施に必要な人員配置について、関係局区との協議状況を伺います。あわせて、区の生涯学習支援部門の職員の執務場所とその理由を併せて伺います。
教育次長:次に、区の生涯学習支援部門の職務内容等につきましては、区全域における社会教育振興等を図ることができるよう、事業を精査し、市民館長会議等での議論を行うなど、その執行体制を含め、関係局区と協議を行っているところでございます。また、職員の執務場所につきましては、区役所の関係部署との連携をより深めることができるよう、区役所内に設置するとともに、市民団体や指定管理者と緊密な連携が図られるよう、市民館内にも執務スペースを設けてまいります。
押本:次に、危機管理対策についてです。中原市民館は、令和6年3月に改定された武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画において、要配慮者を優先に受け入れる一時滞在施設とされています。マニュアル作成及び受入れ体制の確保について、対応を具体的に伺います。次に、モニタリングについてです。令和6年2月、文教委員会にて、利用者アンケートや利用者懇談会の結果をフィードバックする仕組みを明記するよう要望しましたが、その後の対応を伺います。次に、選定評価委員会についてです。仕様書や応募フォーマットには、事業者の取組や力量を見るために、あえて詳細な記述はないとのことです。これまでの本市の市民館・図書館の役割や今後の在り方などを理解した選定評価委員会が審査を行うべきと考えますが、委員会の構成について伺います。また、本市では初となる市民館・図書館の指定管理者の選定に当たっては、適切な評価項目の設定、委員への丁寧な事前説明、書類のみならず応募事業者によるプレゼンテーションの実施、審査時間の十分な確保など、適切な選定プロセスの確保が必要と考えます。見解と対応を伺います。
教育次長:次に、中原市民館についてでございますが、中原区内の一時滞在施設につきましては、共通の帰宅困難者用一時滞在施設受入れマニュアルを区役所で作成し、現在はこれに基づき要配慮者への対応も行うこととしておりますが、今後、マニュアルの改定を検討しており、指定管理者制度導入後も指定管理者と調整しながら、一時滞在施設として十分に機能するよう取り組んでまいります。次に、モニタリングにつきましては、指定管理者は、聴取した市民意見について、管理運営の改善に努めるとともに、市民への説明責任を果たす仕様としたところでございます。次に、局民間活用事業者選定評価委員会の構成につきましては、本市附属機関の委員経験者など、社会教育に関する専門家や図書館に関する専門家等、計5名の専門的知識または経験を有する者を選任しております。また、評価に当たりましては、適正に行うことが重要と考えており、市民サービスの充実等に向け、事業計画等に対する評価項目を設定し、委員への事前の説明を行った上で、応募事業者によるプレゼンテーションを実施するとともに、十分な審査時間を確保してまいります。
押本:次に、議案第110号、等々力緑地再編整備・運営等事業の契約の変更についてに関連して伺います。初めに、整備期間中の代替施設確保についてです。5月のまちづくり委員会資料で工事工程の予定が示され、これまで懸念してきた整備期間中の施設利用について、多くの利用団体に影響が及ぶことが明らかになりました。当該スポーツ団体への説明及び代替施設確保が急務です。見解と対応を伺います。特に、少年サッカーは、大会が開催される旧運動広場、多目的広場の利用が制限される上、第2サッカー場も同時に整備が開始されるため、多摩川河川敷等の多目的広場を活用する必要があり、所管局区等との連携が不可欠ですが、対応を伺います。さらに、各施設においては、工事期間・内容の精査や供用開始時期の工夫等により、利用停止期間の短縮も可能と考えますが、見解と対応を伺います。加えて、新たに整備される催物広場ですが、これまでも子ども会のドッジボール大会やイベント等に使用されてきたことから、各スポーツ施設の代替施設として活用できるよう、隣接の道路面に対して防球ネット等の整備を求めますが、見解と対応を伺います。次に、新テニスコートについてです。公園北側へと移設されるテニスコートは、施設拡充が図られる一方、隣接する地域の方々より音に対する懸念が示されてきました。これまでも継続して丁寧な対応と改善策の検討を求めてきましたが、見解と対応を伺います。
建設緑政局長:次に、等々力緑地再編整備・運営等事業についての御質問でございますが、初めに、整備期間中において利用停止が見込まれる施設につきましては、停止期間中においても既存施設の機能を提供することが基本と考えておりますので、現在、事業者と共に関係団体や関係局と協議調整を進めているところでございます。なお、とどろきアリーナと陸上競技場については、新施設の完成後に既存施設を解体することで、停止期間が生じないよう検討を進めているところでございます。次に、サッカー場につきましては、整備期間中においても既存施設の利用が可能となるよう調整しているところでございまして、仮に利用停止が生じる場合においても、緑地内外の公共施設等について、代替としての活用を図るよう検討してまいります。次に、施設利用の停止につきましては、利用者への影響を最小限にとどめる必要があると考えておりますので、停止期間が生じる場合には、できるだけ期間を短縮するよう事業者に求めてまいります。次に、新催物広場につきましては、現時点では代替施設としての活用はございませんが、施設利用団体へのヒアリングなどを踏まえ、事業者と共に必要に応じて調整してまいりたいと考えております。次に、新テニスコートにつきましては、これまでにも音について御意見をいただいている近隣住民の方に対して定期的に説明を行っており、今後、敷地境界付近に新たに植栽帯を設けるなど、必要な対応を予定しているところでございます。
押本:次に、来場者の想定についてです。球技専用スタジアムをはじめ、新たな施設の竣工により来場者数の増加が想定されています。再編整備前後におけるピーク時の来場者想定について伺います。特に、アクセスの課題については、これまでの大規模イベント時の混雑状況を鑑みますと、さらなる混雑が懸念されます。再編整備に当たり、周辺道路の利用状況や駐車場の台数など、どのような調査検討を行い、対策を講じるのか、見解と対応を伺います。さらに、都市計画の変更に伴い活用したパーソントリップ調査の想定と実際の状況とは乖離が見られます。実態調査を実施すべきと考えますが、見解と対応を伺います。加えて、自転車での来場も相当数想定されており、自転車専用道路の整備や駐輪場の確保について、見解と対応を伺います。
建設緑政局長:次に、等々力緑地の来場者につきましては、再編整備において、球技専用スタジアムなど各施設の規模の変更や新たな機能の導入により増加することを想定しております。また、アクセスの課題につきましては、パーソントリップ調査や交通量調査の結果により現況を把握し、国の指針やマニュアル、現況の駐車場利用実態を基にピーク時の利用想定を行っているところでございまして、想定した再編整備後の発生集中交通量を基に交通管理者と協議を行い、対策が必要となった場合については適宜対応してまいります。次に、交通量の想定につきましては、周辺道路の実態調査を事業者が実施しており、パーソントリップ調査と実態調査を組み合わせて将来交通量の算定を行っているところでございます。次に、自転車での来場への対応につきましては、必要な駐輪台数を確保するとともに、自転車通行環境の整備につきましても適切に対応すべきものと考えております。以上でございます。
押本:次に、新とどろきアリーナについてです。初めに、障害者スポーツについてです。新アリーナは、スポーツセンターやプールを併設します。我が会派は、これまでも何度もパラスポーツ推進の拠点となるよう障害者スポーツ施設の整備を求め続け、その都度、歴代の市民文化局長や副市長から、パラムーブメントの理念浸透を図るとともに推進する等の答弁を受けてきました。さらに、令和4年第5回定例会では、市民が地域で身近にパラスポーツをはじめスポーツ活動を行うための中核施設となるよう、整備内容や管理手法等について関係局区と連携し協議を進める旨、答弁されています。ところが、まちづくり委員会で示された資料には、光に過敏な方向けのセンサリールームや、音に過敏な方向けのカームダウン室を整備することは示されているものの、現状では、プールの仕様をはじめ、今回の整備を新たな機会と捉え、障害者スポーツの拠点となるような施設を目指しているとは言い難い状況です。これまでの議会答弁をどのように受け止め、落札業者との協議に生かしてきたのか具体的に伺います。また、障害者が気軽にスポーツを楽しめる施設として、どのような整備を目指しているのか具体的に伺います。
市民文化局長:次に、新とどろきアリーナ等についての御質問でございますが、本市では、かわさきパラムーブメントの目指す共生社会を実現するため、レガシーとして掲げる誰もがスポーツ、運動に親しんでいるまちの形成に向け、取組を進めてまいりました。こうした中、等々力緑地に整備する新たな屋内スポーツ施設につきましても、これまでに議会をはじめ様々な団体からいただいた御意見等を踏まえ、障害者や高齢者も利用しやすいスポーツ施設として整備することなどを要求水準に定めたものであり、この内容が基本設計に反映されるよう事業者等と協議調整を重ねた結果、障害のある方に配慮したハード面の整備に加え、現行の施設では未整備となっていたカームダウン室等の設置が基本設計に盛り込まれたところでございます。これまでも本市では、各スポーツセンターや中部リハビリテーションセンター附属運動施設等での障害のある方を対象としたパラスポーツ体験会の開催や、プールでの専用コースの設置等の取組を通じてパラスポーツを推進してまいりました。今後も、こうしたソフト面のさらなる充実に加え、新たな屋内スポーツ施設につきましても、要求水準の内容が適切に基本設計や実施設計に反映されるよう引き続き取り組んでいくとともに、パラスポーツに関連する本市の取組や各種大会などの情報を一元化し、広く市民向けに広報、発信する機能や、障害のある方が身近な地域でパラスポーツに親しめるよう、近隣のスポーツセンター等へ円滑かつ適切につなぐ機能等を備えた拠点施設としての運営面の取組や、パラスポーツ用具の配備等につきましても、今後、事業者等と協議調整を進めてまいります。以上でございます。
押本:次に、二十歳を祝うつどいについてです。これまでは午前と午後に分け、アリーナで一堂に集まり実施をしてきましたが、令和4年度からは、周辺住民の車両も規制した上、等々力緑地一帯を通行止めにして行っています。こうした状況に当事者や保護者からは不満や、運営方法の改善、変更を求める声が寄せられています。再編整備により今後様々な施設の運用が開始されますが、そのような状況で現在の開催手法が継続できるのか疑問です。事業者とはこの点についてどのような話合いがなされているのか具体的に伺います。
これまでも我が会派は、二十歳を祝うつどいを各区で開催することを提案してきましたが、再編整備を改革の機会と捉え、この件について庁内で改めて議論することが必要と考えます。市長に見解を伺います。
市長:二十歳を祝うつどいについての御質問でございますが、式典に参加する青少年の意識や価値観なども多様化してきており、青少年の声も聴きながら、開催の目的や内容について検討する必要があるものと考えております。今後につきましては、二十歳を祝うつどいに参加する世代を対象にヒアリングやアンケートを実施するなど、開催場所や内容につきましても、共に開催に当たる青少年関係団体とも十分な議論をしながら検討してまいりたいと存じます。
こども未来局長:二十歳を祝うつどいについての御質問でございますが、事業者である川崎とどろきパーク株式会社からは、令和8年以降の3年間、アリーナ周辺の広場などの設備が工事により一部使用できないと伺っており、主に参加者の安全確保を第一に考えながら意見交換を行っているところでございます。以上でございます。
押本:次に、議案第115号、令和6年度川崎市一般会計補正予算について伺います。初めに、小中学校の自然教室運営事業費についてです。これは令和6年1月に公示された令和6年度自然教室運営委託の3月の入札不調により発生したものです。令和6年度当初予算は、小中学校合わせて前年度比約3,637万円増の約1億8,452万円でしたが、結果として、さらに9,632万円の増となりました。要因及び来年度に向けての改善策を伺います。この要因につきましては他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。
また、これにより一部の学校で日程や行き先の変更が生じたとのことです。民間施設や県の施設に行くことになった場合の追加費用の保護者負担の考え方について伺います。さらに、本市の就学援助制度では、自然教室に関する補助は食事代3,140円となっていますが、保護者負担が増加した場合、その範囲を超えた分についての対応を伺います。あわせて、次年度以降の対応について伺います。次に、教員の負担軽減についてです。自然教室の3日間のうち、2日間が土日にかかる日程となった場合の教職員等の負担増や代休の確保について、見解と対応を伺います。次に、貸切りバスの確保についてです。現在、確保が極めて困難になっていることについては、自然教室のみならず、修学旅行や校外学習に関しても大きな影響があると考えます。各学校に注意喚起をし、早めに準備を促すべきと考えますが、具体的な対応を伺います。
教育次長:次に、自然教室運営事業費についての御質問でございますが、初めに、改善策につきましては、自然教室の着実な実施に向け、事業者ヒアリング等を行いながら、早期のバスの確保に向けた対応を進めてまいります。次に、他施設を利用する場合につきましては、八ケ岳少年自然の家を利用した場合と同様に、食事代や体験活動等に係る費用を保護者負担としており、次年度以降の対応につきましては、今後の自然教室の方向性と併せて検討してまいります。次に、食事代として支給する就学援助費の単価につきましては、八ケ岳少年自然の家が設定する食事代と同額としており、他施設を利用する場合には、当該施設の食事代に基づいた設定について検討してまいります。次に、教職員の週休日につきましては、各学校の状況に応じて週休日の振替等により確保しているところでございます。次に、その他の学校行事についてでございますが、現時点では修学旅行への影響は出ておりませんが、自然教室における入札不調の状況やバス運転手の不足に伴う早期対応の必要性について、各学校に情報提供し、貸切りバスから鉄道や路線バスでの移動に切り替えたり、日程や実施場所を変更したりした行事があることを把握しているところでございます。以上でございます。
押本:以上で質問を終わりますが、答弁によっては再質問いたします。
押本:それぞれ答弁をいただき、ありがとうございました。それでは、再質問いたします。
まず、障害福祉サービス事業所の不祥事への対応についてです。初めに、統一した処分量定基準を国が示すことへの要望について、本市が単独で国に働きかけるよりも、障害福祉サービス事業所の指定権限を持つ、例えば9都県市などの枠組みで連携して対応することがより効果的と考えます。速やかに国から処分量定を発出させるための取組として、他都市との連携について伺います。次に、昨年秋に、全国の都道府県、政令市、中核市など障害者グループホームの指定権限を持つ180自治体に厚生労働省の委託調査が行われたと仄聞します。その報告書によると、指定権限を持つ自治体の9割が事前の研修を実施していないことなど、開設後の質確保向上の取組について課題が浮き彫りとなりました。本市のアンケートに対する回答内容について伺います。さらに、グループホーム開設について、川崎市が指定行為に義務づけていない法人への事前研修をはじめ、開設後の質確保に向けた取組、開設前に自治体が新規事業者を評価する仕組みなどについて、今後の取組の在り方を伺います。
次に、五反田川放水路整備事業及び関連事業についてです。議会への報告については、2年もの時間を要し、申し訳ないとした一方、この間、議会からは浸水想定面積に係る指摘がなかったとの答弁でした。当局のこの消極的な姿勢は、災害対策に直結することからも、議会に対する説明責任の欠如と指摘せざるを得ません。改めて見解と対応を伺います。以上です。
健康福祉局長:障害福祉サービス事業所に対する勧告についての御質問でございますが、処分量定につきましては、本市としても裁量権や公正性の観点から、国による統一した基準が必要であると認識しているところでございますので、21大都市心身障害者(児)福祉主管会議等の様々な機会を活用しながら、引き続き国に対し積極的に要望してまいりたいと存じます。障害者グループホームに係る厚生労働省の調査につきましては、本市としては回答しておりませんが、質の確保向上の取組といたしましては、グループホームの新規開設及び定員増を希望する事業者に、指定申請を行う前年度に選定委員会を行い、一定の評価以上の事業所について承認手続を行う川崎市障害者共同生活援助事業所選定委員会を実施してきたところでございます。今後につきましては、国等が実施する調査等に積極的に協力するとともに、調査結果から抽出される課題を踏まえ、引き続き質の確保向上に向けた取組の検討を行ってまいりたいと存じます。以上でございます。
建設緑政局長:五反田川放水路整備事業等についての御質問でございますが、今後につきましては、今回の事象をしっかり受け止め、事業進捗の変更等があった場合には速やかに報告し、治水安全度の向上に向け取り組んでまいります。以上でございます。
押本:それでは、意見要望を申し上げます。
まず、出資法人等への再就職についてです。今回の質疑では、出資法人等のトップが交代するに当たり、本市に求人を依頼する際、法人内での意思決定過程が人事課及び法人所管部署で確認されていないというずさんな実態が明らかになりました。また、本事案に対し、議会側から課題を指摘されなければ、人事課及び法人所管部署が率先して出資法人の人的関与に関わる事案について、透明性を図ろうという意思が働いていなかったことは遺憾です。さらに、選考委員会委員から有意義な意見が出ているにもかかわらず、人事課が意見を尊重していないことは、委員会の存在が形骸化し、結果としてこの委員のモチベーションが低下する遠因にもなりかねません。出資法人等のトップの人事については、ブラックボックスで決定されるのではなく、意思決定過程を明らかにすること、人事課は選考委員会委員の意見を十分活用すること、この2点を着実に実行するよう強く求めておきます。
次に、北部市場の機能更新計画について意見要望を申し上げます。さきの質問では、北部市場の青果物と水産物の経由率が、それぞれ18.5%、38.3%であることが明らかになりました。市民の食の安定供給を大目的とする公共性の担保について、疑問符がつく北部市場の低迷状況です。さらに、今回の市場更新計画の売場施設等の規模を算定した前提条件である北部市場3部門における将来取扱量、2035年の推計値と2023年度の実績値を比較したところ、既に青果部、水産物部、花卉部のいずれも現時点で推計取扱量を下回っている現状も明らかになりました。特に、水産物部の激しい落ち込みが顕著です。本年3月に策定されたばかりの基本計画の売場施設等の規模の算出条件が、僅か3か月で既に破綻している現状を深く憂慮せざるを得ない事態です。このような現状において、62年間の総事業費1,450億円のうち、1,002億円を市場使用料で充当するこのスキームです。よって極力総事業費を圧縮し、場内事業者が負担する市場使用料の低減を図ることが必須の条件と考えます。そのための市場整備のダウンサイジング、最適化を提案し続けてきました。更新整備事業者の選定までの期間に、要求水準書の見直しを含めた施設全体の適正なダウンサイジングの検討を強く求めておきます。
次に、神奈川県川崎競馬組合の移転についてです。同組合は、優先交渉権事業者として小向厩舎及び練習馬場の移転について神奈川大学と交渉を進めるとのことです。答弁にもあるとおり、これらの移転は本市にも大きな影響を与える課題であると考えます。現在の厩舎と練習馬場を合わせた敷地面積は約16ヘクタールあり、多摩川河川敷にある練習馬場の跡地活用については、スポーツ施設の整備など市民ニーズを踏まえた上で、国をはじめとする関係者に対し早期に働きかけを行うよう要望をいたします。
次に、社会福祉法人母子育成会に対する監査結果についてです。まず、健康福祉局及びこども未来局が、少なくとも平成28年度から、当該法人の経営状況が悪く、不正な会計処理が行われていたという事実を把握しながら、議会への情報提供がないまま、法人が所有する施設に対し、約2億5,600万円もの整備事業費が予算計上されていることについては、そもそも、不正を働いた法人に対し、その法人の経営や運営等の改善が図られているのか十分確認した上で予算支出を行うべきであり、全容を知らぬまま多額の事業費を計上したことは疑問が残ります。監査が進行中であり、情報の取扱いは慎重にならざるを得なかったことは理解しますが、今後も議会との連携は十分図るよう求めておきます。また、健康福祉局によるこれまでの監査については、より踏み込んだ対応が必要であったと考えます。口約束で相手方を信頼するのであれば監査の必要はありません。過去には複数の市OBを含む関係者が当該法人の運営に関わっていたことからも、法人が長年にわたり本市の福祉利権の温床になっていたとの批判は免れません。まずは今回の事案を教訓として健康福祉局の監査部署の増員を図り、組織体制を強化した上で監査の充実を図ることや、本市から法人へ支出された補助金等の目的外使用については、適切に精査した上で、着実に返還を求めることを強く求めておきます。
次に、障害福祉サービス事業所の不祥事への対応に関連して意見要望を申し上げます。昨年秋の障害者グループホームに係る厚生労働省の調査について、所管課の共有メールに調査の回答依頼があったにもかかわらず、一係員に任せきりで課全体として業務の共有がなされなかったことにより、その回答を失念したことは重大な失態と指摘せざるを得ません。情報共有の在り方については、所管部署内のみならず健康福祉局全体の課題と捉え、綱紀の粛正を強く求めておきます。
最後に、まちづくり局の度重なる人為的ミス及び組織マネジメントについてです。藤倉副市長からは、工期の遅れやさらなる費用負担について謝罪と、職員一人一人が緊張感を持ち職責に励むとの御答弁がありました。答弁については理解しましたが、まちづくり局の事務ミスはとどまることを知らず、これらは全て今後の内部統制評価報告書にも記載されるほどの案件です。処分することが目的ではありませんが、巨額の公金損失が生じながら、局内において注意すらされていないことは、社会通念上、市民に理解されるものではなく、モラルハザードの元凶となり、ひいては同様の人為的ミスは続くことが予想をされます。昨年から続く市民館、労働会館の増額、関係局との連携不足により工期延長した坂戸小学校事案、下布田小学校体育館改修工事に伴う積算ミスなど、まちづくり局が原因で生じた公金損失を積み上げると既に数億円規模になっています。さきの定例会では、副市長より、同様な事案が発生した場合は、原因なども厳格に精査した上で適正に評価をしていくとの答弁でした。人為的ミスが止まらないのであれば、処分や人事評価を厳格に行うなど、信賞必罰は徹底するよう求めておきます。
あとは委員会に譲り、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
副議長:お諮りいたします。本日はこの程度にとどめ延会することとし、次回の本会議は明日12日の午前10時より再開し、本日に引き続き代表質問等を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり
副議長:御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。
副議長:本日はこれをもちまして延会いたします。