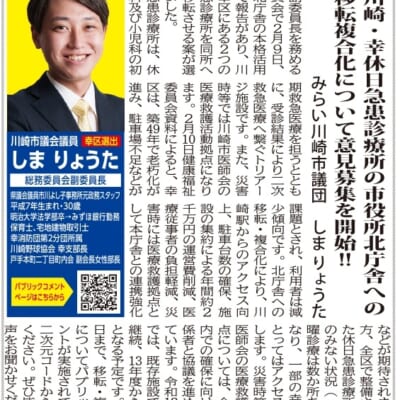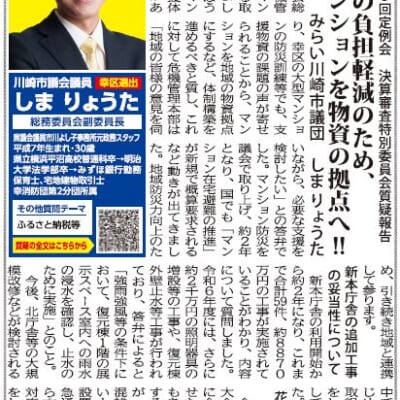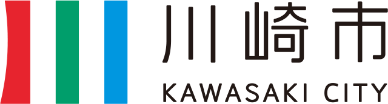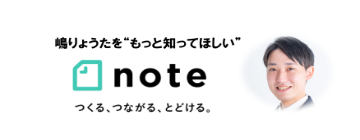しま:次に、13款8項5目社会教育施設再整備事業費、幸市民館・図書館老朽化対策等基本計画策定支援業務委託料について伺います。
はじめに、令和5年度の決算額は、約3,354万円、不用額が約131万円となっていますが、事業内容と不用額の要因を伺います。あわせて、今年度の取組を伺います。
生涯学習推進課担当課長:幸市民館・図書館老朽化対策等基本計画策定支援業務委託料についての質問でございますが、事業内容につきましては、幸市民館・図書館の老化対策の内容や範囲の検討及び基本計画案の策定作業の支援等を委託するものでございまして、不用額は、契約差金によるものでございます。
また、今年度の取組につきましては、5月に基本計画案を公表し、パブリックコメント手続を経て、8月に基本計画を策定したところでございまして、10月上旬の入札を経て、実施設計に着手する予定となっております。
しま:次に、改修基本計画についてです。構造躯体調査の参考資料の鉄骨調査においては、梁について「設計図と異なる部分はあった」「取り付け位置が図面と異なる」と記載があります。そのような箇所が他にもなかったのか、確認できたのか伺います。また、実施設計及び改修工事への、遅れ等の影響はないのか伺います。
生涯学習推進課担当課長:構造躯体調査についての御質問でございますが、令和3年度に実施した鉄骨部材調査においては、梁の一部に設計図と異なる部分があること等を確認しましたが、構造上の問題はないとの報告を委託事業者から受けており、また、それ以外に設計図と異なる部分はないことから、今後の実施設計や改修工事への影響はないものと考えております。
しま:次に、関係法令適合状況調査では、現在は既存不適格という結果でした。先日のパブリックコメントでは、意見が寄せられ、回答は「構造上、一部対応できないものもあります」とのことでしたが、内容を具体的に伺います。また、改修後も既存不適格となるのか伺います。あわせて今後の対応について具体的に伺います。
生涯学習推進課担当課長:関係法令適合状況調査についての御質問でございますが、大会議室前へのスローブの設置や舞台に上がる経路確保など、今回の改修で対応できる既存不適格の箇所につきましては、実施設計の中で検討してまいりますが、大ホールのスロープや舞台裏の通路は、今回の改修後も「川崎市福祉のまちづくり条例」が定める140cm以上の幅員が確保されず既存不適格となり、職員によるサポートなど、運営面での工夫により適切に対応してまいります。
しま:次に、幸市民館・図書館における地域イベントについてです。先週土曜日に、幸市民館にて第9回市民館ジャックが行われました。地域の子どもたちが市民館を占領し、子どもたち自身が企画、運営をし、「おばけ屋敷」や「だがし屋さん」など、約20にわたるブース等に加え、ホールステージでのダンスや演奏の披露などが催され、私も現地で参加しましたが、会場いっぱいのこども保護者のみなさんで活況でした。これまでも様々な関係団体等に意見を伺っているとのことですが、例えば、委員会報告資料では、2階廊下に書架とサイレントスペースを配置するとのことですが、イベント時には、参加者の動線となりえることが想定されます。諸室の配置等を含め、イベント主催者や関係団体等から寄せられた意見と本市の見解について伺います。また、施設の利用方法の整理や利用者の理解も不可欠です。指定管理者制度が導入予定ですが、改修工事があることから、改修前の地域イベント等についてどの程度、状況等を把握した応募者が出るのか懸念されます。改修工事と同時並行で指定管理者の選定が行われることに対しての課題と対応を伺います。
生涯学習推進課担当課長:幸市民館・図書館についての質問でございますが、改修基本計画の策定に当たり、昨年度から地域団体へのヒアリングやワークショップにおいて市民意見を聴取してまいりましたが、「市民館ジャック」を主催している幸区地域教育会議からは、「2階にも図書館を配置すると、静かにしなければならず、にぎやかなイベントがやりづらくなる」等の意見をいただいており、今後、実施設計を行う中で、諸室の配置やレイアウト等について検討するとともに、イベント時には図書館利用者等への事前周知の徹底を図ってまいります。
また、改修工事と指定管理者の選定予定時期が重なるため、関心のある事業者が、実際の施設・設備や運営状況等を確認できないといった課題がございますが、市ホームページや川崎市PPPプラットフォーム等を活用しながら、改修後の施設・設備や、これまでの運営状況等について情報提供を行ってまいります。
しま:要望です。ジャック当日は現地も見ていただいたということでありがとうございました。改修後の話もあり、かなり先の話になりますが、引継ぎ等しっかりしていただき、対応していただくようお願い致します。あわせて、工事中の代替機能の確保も引き続き、課題ですので、関係団体等とコミュニケーションとっていただきながら、対応していただくよう委員会等でお願いしておりますけども、重ねてお願い致します。
しま:次に、13款8項2目のうち学校施設長期保全計画推進事業費について伺います。
はじめに、令和5年度の決算額は、総額約65億円となっていますが、内訳について伺います。
教育環境整備推進室担当課長:学校施設長期保全計画推進事業費についての御質問でございますが、令和5年度の内訳につきましては、校舎が、設計26校、設計及び工事8校、工事8校の計4 2校、体育館が、設計20校、工事3校の計2 3校、直結給水化が、設計14校、工事6校の計20校となっております。
しま:次に、本定例会わが会派代表質問において、体育館への空調導入を求め、学校施設長期保全計画の見直しについて質問し、検討していくとの答弁でした。前定例会一般質問では、河原町体育館が使えなくなったあとの代替避難所の体育館も再生整備となり、利用できなくなる状況を指摘しました。災害時に利用される公共施設等の改修、改築についても可能な限り、配慮すべきです。また、幸区内では、古川小学校では体育館再生整備、下平間小学校では校舎再生整備が行われており、約200mしか離れていない隣接地域の学校で、どちらも校庭が一部利用できず、地域の利用団体等の大きな負担となっています。こうした現状から、本計画の見直しと対応について伺います。
教育環境整備推進室担当課長:学校施設長期保全計画推進事業費についての御質問でございますが、同計画に基づく再生備等の工事時期につきましては、学校施設の老化に適切に対応するため、築年数を基本として計画しており、隣接地域でも工事を実施していく必要がございます。また、工事期間中の校庭につきましては、学校運営等に配慮して必要最小限の範囲を工事ヤードとして設定していることや、地域の行事日程を踏まえた工事工程の調整を行っているものの、校庭の利用に制限が生じることとなり、地域の皆様が利用される場合に御不便をおかけいたしますが、御協力をお願いしているところでございます。
しま:次に、学校施設の校舎の断熱化について伺います。学校施設の暑さ対策は喫緊の課題であり、空調整備とともに断熱化も重要です。本市の長期保全計画のAグループ、Bグループ、Cグループのそれぞれの断熱化の状況と、工事内容等の違いがあれば伺います。
教育環境整備推進室担当課長:学校施設長期保全計画推進事業費についての御質問でございますが、令和6年3月末時点の校舎の断熱化の実施状況につきましては、平成25年5月時点で築年数が20年以下のAグループは6校、築年数が21年以上30年以下のBグループは15校において、ウレタンゴム系塗膜防水断熱工法による屋上の断熱化を実施したところでございます。
また、築年数が31年以上のCグループの27校につきましては、劣化の進行や機能の低下が想定されるため、屋上の断熱化とともに、内装改修に併せ、発泡ウレタン断熱材の吹き付けによる壁の断熱化や、複層ガラスの設置による窓の断熱化を実施し、加えて、Cグループの49校につきましては、劣化の進行を抑えるため、防水工事に併せ、屋上の断熱化を実施したところでございます。
しま:次に、Aグループ、Bグループに属する学校の関係者の方々から、特に最上階の教室が空調をつけても暑く、「勉強に集中できない」「他の教室に移動している」等の声が寄せられています。断熱化の詳細の状況を早急に確認し、長期保全計画において整備メニューの校舎予防保全①や校舎再生整備①に断熱化を追加し、優先度を上げて整備すべきと考えますが、見解と対応を伺います。
教育環境整備推進室担当課長:学校施設長期保全計画推進事業費についての御質問でございますが、各グループの断熱化につきましては、同計画に基づき 実施しており、A、Bグループについては、現在実施して いる整備メニューに断熱化の記載はないものの、屋上の 断熱化を防水改修と併せて行っているところでございまして、今後、壁及び窓の断熱化は内装改修の実施時期に併せて行ってまいります。また、Cグループについては、築年数の経過により劣化が進行しているため、校舎再生整 備の中で、断熱化を実施しているところでございます。なお、教室の暑さ対策につきましては、昨今の猛暑による教室の状況を踏まえると、重要であると認識しておりますので、既存の空調設備が更新等の時期を迎えている ため、今年度から、これらの空調設備の一斉更新等の事業を着実に進めてまいります。
しま:次に、市民主体の教室断熱化の取組についてです。保護者や地域住民、企業が協力し、主体となり、教室を断熱化する断熱ワークショップの取組が全国各地で実施されています。資金の調達方法から実現方法までまとめられたマニュアルもあり、本市においても実際に動き出している市民の方もいます。こうした自発的な活動においては、本市も可能な限り協力すべきと考えますが、見解と対応を伺います。
教育環境整備推進室担当課長:保護者等による取組についての御質問でございますが、学校の施設・設備につきましては、原則として、市が公費で整備するものと認識しておりますが、市に整備計画がない場合や、計画はあるものの整備までに時間を要する場合には、保護者等の自発的な取組として、寄附していただく仕組みもございます。施設・設備の寄附受納につきましては、性能及び安全性等の観点から、一定の水準を満たす必要があることや、教育活動や学校運営上の活用に関する学校の意見等が重要であると考えておりますので、事案に応じて事前相談等の対応を行ってまいります。
しま:要望です。まず、長期保全計画についてです。老朽化の対応のため、隣接地域等でも工事を進めていくとのことですが、災害対策の観点からも地域での避難所の確保は重要です。前回の一般質問でも指摘しましたが、危機管理室との連携はとても大きな課題だと思います。しっかり公共施設の工事等の地域事情もしっかり把握していただいて計画と実施するようお願い致します。次に、学校教室の断熱化についてです。学校現場から、暑いといった声が当局にも届いていると伺っております。現場の状況を把握していただき、断熱化、空調の整備と連携し、速やかに暑さ対策を進めていただくようお願い致します。あわせて、市民の自発的な取組についても丁寧な対応と、後押しをしていただくようお願い致します。
しま:次に、13款1項5目海外帰国・外国人児童生徒等関係事業費について伺います。
はじめに、令和5年度の決算では、約550万円予算が不足、令和4年度も約1080万円不足していますが、それぞれ要因を伺います。
教育政策室担当課長:海外帰国・外国人児童生徒等関係事業費についての御質問でございますが、本市では、市立小中学校における学校生活への適応と日本語学習の支援として、委託業者が派遣する対象児童生徒の母語を話せる支援員による「日本語指導初期支援」を行っておりますが、支援を必要とする児童生徒が増加している中、この支援に係る総時間数は、年々増加しているところでございます。予算が不足した要因につきましては、日本語指導初期支援が必要な児童生徒数を正確に予測することが困難であり、対象児童生徒の増加が想定を上回ったことから、委託料を増額して、対応したところでございます。
しま:次に、委託状況についてです。令和2年度から始まり、公募型プロポーザルで業者を決めているとのことですが、これまでの応募状況について伺います。また、契約内容について伺います。あわせて、課題と今後の対応について伺います。
教育政策室担当課長:日本語指導初期支援についての御質問でございますが、はじめに、応募状況につきましては、公募型プロポーザルにより、和2年度は2者、令和3年度は2者、複数年契約とした和4年度・5年度は1者、令和6年度から8年度までは1者となっております。
次に、契約内容につきましては、一人当たり合計100時間の支援を行うことを原則とし、対象児童生徒の母語を話せる支援員が、初期の日本語指導と学校生活への適応支援を行っているところでございます。こうした中、対象児童生徒の増加や多言語化を背景に、支援員の確保が課題となっております。現在の契約では、近年の賃金上昇に対応するため、支援の1時間当たりの単価を増額するとともに、契約期間を3年として支援員が働きやすい環境を整えたところでございまして、今後も、受託事業者と協力し支援員の確保に努めてまいります。
しま:次に、支援の内容についてです。原則100時間、個別に支援としていますが、支援状況について伺います。また、支援の質等については、どのように把握しているのか伺います。あわせて、過去の答弁においては、「個々の児童生徒の状況に応じた適切な初期支援の時間数についても検討していく」旨の答弁でした。予算の執行状況や、対象児童生徒数も急激に増えていることから、個々の状況に応じた支援時間や支援方法を検討すべきと考えますが、検討状況を伺います。
教育政策室担当課長:日本語指導初期支援についての質問でございますが、はじめに、支援状況につきましては、受託事業者が専門性を生かしながら指導計画を作成し、対象児童生徒一人ひとりに応じた支援を行っているところでございます。
特に、中学生から支援を開始した生徒につきましては、希望により初期支援実施後の日本語学習を補充するものとして、国語の学習を中心とした支援をさらに50時間追加して実施しております。次に、支援状況の把握等につきましては、学校は、支援員が作成した業務報告書により、支援が適切に行われているかを確認し、改善点があれば教育委員会事務局に報告することとなっております。
また、教育委員会事務局には、受託事業者から常駐の管理運営責任者が配置されており、当該責任者から定期的に報告を受け、必要に応じて改善に向けた指導等を行い、支援の質の向上に努めております。
次に、支援の充実につきましては、本市では、母語を活用した100時間の支援により、児童生徒の学校生活の不安の解消につなげており、初期段階の日本語能力の習得に十分寄与していると考えておりますので、引き続き現行の枠組みを維持しながら、更なる多言語化への対応なども含め、児童生徒の個々の状況に応じた取組を進めてまいります。
しま:最後に要望となります。本市の外国籍児童生徒数は昨年度1,752人で過去最多、同様に、日本語指導が必要な児童生徒数についても今年度1,168人で過去最多で、直近5年間でほぼ2倍とのことです。本事業は、他都市よりも力を入れている取り組みということですので、引き続き、質の向上、個々の対応の充実をお願い致します。以上です。