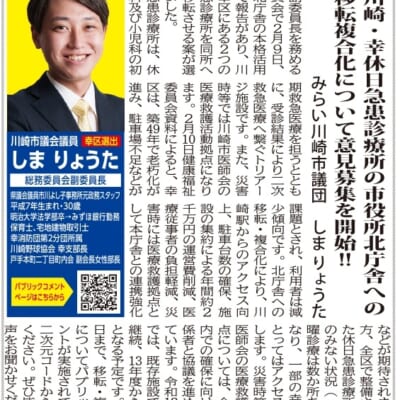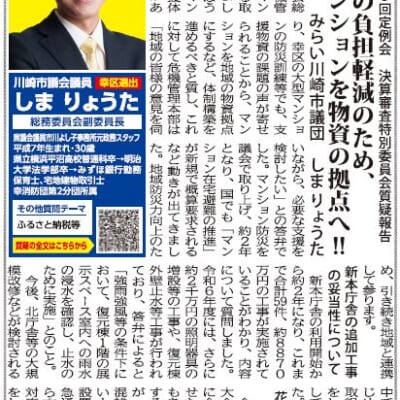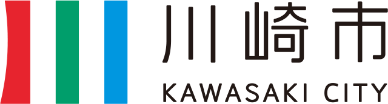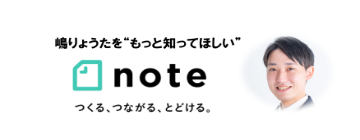リーディングDX事業費等について
しま:私は、13款1項7目GIGAスクール構想推進事業費、12款1項1目火災予防運動事業費、3款1項5目映像のまち・かわさき推進事業費、11款1項3目幸区区づくり推進費について伺います。はじめに、13款1項7目GIGAスクール構想推進事業費のうち、リーディングDXスクール事業費等について伺います。令和7年度の予算額は、令和6年度と同等となっています。生成AIパイロット校の令和7年度の取組と、令和6年度の具体的な取組及び教員からの声について伺います。
教育次長:生成AIパイロット校についての御質問でございますが、今年度につきましては、南河原中学校が、文部科学省の令和6年度「リーディングDXスクール事業」の生成 AIパイロット校に指定され、生成AIの試行利用を行っております。教職員向けのアンケートでは、約64%が「業務が効率化された実感がある」また、約78%が「今後も様々な業務で利用したい」と回答しており、生成AIの有用性や活用拡大の希望が確認されたところでございます。また、他都市の学校を視察した教員からは、「生成AIの授業での活用に対して、具体的なイメージを持つことができた」との感想があったところでございます。次年度につきましては、複数の学校がパイロット校に指定されるよう準備を進めており、生成AIを活用する業務を広げるとともに、命令文であるプロンプトの事例集作成などに取り組んでまいりたいと考えております。
しま:次に、校務での利用についてです。令和6年12月26日に、文部科学省から「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドラインバージョン2.0」が公表されました。また、このガイドラインの公表に向けては、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」で議論がなされてきました。本市のリーディングDXパイロット校の取組のアンケートでは答弁の通り、前向きな結果が出ている一方で、国の検討会議では、前さいたま市教育長から、「パイロット校とそれ以外の学校は別世界である」との発言があり、横展開する際には、課題があることも想定されます。また、つくば市では、「生成AI活用の手引き」を作成し、各校に配布している取り組みもあります。本市の見解と、課題及び課題に対する工夫等、今後の取組を伺います。
教育次長:生成AIについての御質問でございますが校務等で生成AIを利用することは、業務の効率化や質の向上などが期待され、教職員の働き方・仕事の進め方改革に資するものと考えており、パイロット校での成果を全校に広めていくことが重要であると認識しております。生成AIの校務での利用では、個人情報や機密情報の漏洩が課題となりますので、プロンプトに個人情報や機密情報を入力しないことや、生成AIがプロンプトの内容を学習する設定にしないことなどについて、教職員向けの研修において、徹底しているところでございます。今後につきましては、情報教育学校担当者会やGSL向け研修等において、課題への対応策と校務での利用に関する好事例を横展開してまいりたいと考えております。
しま:全市的な着実な取組をお願いします。次に、国のガイドラインでは、教育委員会が抑えておくべきポイントの基本的な考え方として、「生成AIを学校現場で利活用する際には、教育委員会が主導して制度設計や利活用の方向性を示すことが重要であること」「教育委員会には、教員養成系大学やサービス提供者等の外部のリソースも活用しつつ、先行事例や教材・ノウハウを周知・共有することが期待されること」「教職員の生成AIに関する理解を深め、生成 AIを意図的に利活用する場面、生成AIの出力を吟味する時間の確保、深い学びにつながる発問など、効果的な活用を促進する研修を実施することにより、生成 AI の適切な利活用を推進する環境を整備する必要があること」などが示されています。国のガイドラインに対する本市の見解と対応を伺います。
教育次長:生成AIについての御質問でございますが国のガイドラインにつきましては、学校現場において適切に利用するためのポイントが示されているものと捉えており、将来的に、児童生徒が生成AIを利用するためには、情報活用能力をさらに育成する必要があり、その能力を育成する教員の役割が最も重要であると改めて認識したところでございます。今後につきましては、引き続き、国と市のガイドラインの双方を踏まえ、校務等での生成AIの試行利用を進めながら、児童生徒の情報活用能力がさらに高まるよう取り組んでまいります。
しま:年末に公表されたばかりではありますが、スピード感ももった対応と取組もお願い致します。次に、子どもたちの生成AIの利用についてです。大手教育企業の民間調査では、小学生で生成AIを知っている割合が23%で、約4人に1人程度であり、そのうち約7割が利用したことがあると回答しました。また、保護者の66%が生成AIを子どもが利用することに肯定的であり、子どもについては、知っていると回答したうち約9割が利用に肯定的な結果でした。検討会議においても、使い方については、アイデア出しのみならず、AIを使った音読練習による意欲や技能の向上、答えを教えない探求的なAI家庭教師としての利用などの効果的な利活用も紹介され、全7回にわたる検討会議では、社会情勢を踏まえ、利用のリスクだけではなく、有効な利活用について前向きな議論が多くなされていました。本市においても、すでに利用している子どもがいることが想定されると仄聞しますが、子どもたちの利用について、本市の見解と今後の取組を伺います。
教育次長:生成AIについての御質問でございますが、児童生徒が学習活動で生成AIを利用することにつきましては、情報モラルを含む情報活用能力の育成とともに、教員の適切な指導監督の下で利用することが必要であると考えております。現在、本市のGIGA端末では、児童生徒は生成AIを利用できない設定としておりますが、今後につきましては、将来的に児童生徒が生成AIを利用する際に必要となる情報活用能力がさらに高まるよう、学校を支援してまいります。
しま:具体的な支援については、現在まさに検討しているということでしたので、子どもたちの情報活用能力向上にためにも、着実な取組をお願い致します。次に、ガイドラインの導入部分の「ガイドラインの策定に当たって」では、「現行の学習指導要領は、AIの存在を前提として、」「社会の変化が加速し、複雑となるこれからの時代に必要な資質・能力を確実に育成することを目指している。」「AI時代を生きる子供たちが生成AIをはじめとするテクノロジーをツールとして使いこなし、一人一人が才能を開花できるようになることは重要である。」「学習指導要領に示す資質・能力の育成に向けて適切に生成AIと向き合い、利活用することができるよう」、策定されたとのことです。このような国の状況を踏まえ、本市としても、実態把握をし、改訂が予定されている「かわさき教育プラン」や「情報化推進計画」等に、生成AIの取組について明確に位置付け、具体的な取組を検討すべきと考えますが、本市の見解と対応を伺います。
教育次長:生成AIについての御質問でございますが、生成AIの適切な利用に向けましては、環境の整備や研修会等による教員の支援などを推進することが重要であると認識しており、次年度のパイロット校における試行利用状況や効果を把握した上で、社会の変化や国の動向などを注視しながら、次期情報化推進計画等の策定の中で検討してまいりたいと考えております。
しま:要望です。令和5年6月一般質問で教育現場での生成AIの利用について、教育長は、「現時点では、その有効な活用可能性よりも課題の大きさが論じられていると認識している」との答弁でした。それからたった約1年半余りで、社会情勢も大きく変わり、ガイドラインにおいても、「生成AIの存在を踏まえた情報活用能力の育成強化」が明記され、当然ながら本市の取組も必須となりました。今回の議論で様々確認し、進めていただきましたが、時代の流れが速く、変化が激しい分野ですので、今後もしっかり社会情勢、国の動向等をキャッチしていただいて、取り組んでいただくようお願いいたします。
火災予防運動事業費について
しま:次に、12款1項1目火災予防運動事業費について伺います。令和7年度予算が、倍程度増額されていますが、理由及び来年度の取組を伺います。
消防局長:火災予防運動事業費についての御質問でございますが、火災予防運動事業費につきましては、地震体験車を活用した訓練指導について業務委託する事業費及び火災予防啓発物品の購入の事業費でございまして、増額の理由といたしましては、業務委託に要する人件費の変動等によるものでございます。来年度の取組といたしましては、地震体験車の活用につきましては、引き続き市民の防火・防災意識の向上のため、市内で実施される消防訓練、自主防災訓練等に派遣し、訓練指導を行ってまいります。また、火災予防啓発物品につきましては、引き続き火災発生状況等を踏まえまして、各種イベント等で活用する広報物品を購入し、配布してまいります。
しま:地震体験車関係について体制が手厚くなるよう調整中とのことですので、より多くの地域要望等に対応できるよう要望しておきます。次に、火災予防についてです。令和6年の本市の火災の発生状況について伺います。また、近年の傾向についても伺います。あわせて、そのような状況を踏まえた、今後の火災予防の取組について伺います。
消防局長:火災予防についての御質問でございますが、はじめに、令和6年の火災件数につきましては、398件でございまして、これは過去10年間で最多となっております。また、火災原因といたしましては、電気機器、たばこ、こんろ、放火が上位となっております。
しま:次に、近年の火災の傾向につきましては、電気機器や 配線器具などに起因する、電気火災が増加しているところでございます。そのような状況を踏まえまして、電気火災を防ぐため、モバイルバッテリーなどには強い衝撃を与えない、電気コードを束ねたり、重いものを載せたりしないなどの具体的な対策を、分かり易く表現したチラシの配布やホームページによる発信等を行ってきたところでございますが、今後、これまで以上に積極的な広報活動を行ってまいりたいと存じます。新たなSNSを昨年末に開設していただいたと聞いていますので、さらなる積極的な広報をお願い致します。火災件数については、過去10年間で見ると、全国的には近年多少増加はあるものの漸減傾向である一方、本市は令和6年が最多となり、令和5年に続いて2年連続になります。また、昨年の幸区の火災発生状況においては、令和5年32件から令和6年69件と、倍以上の増加となりました。主な増加要因の一つとして、昨年夏ごろのいわゆる連続放火事件がありましたが、本市の対応を伺います。また、教訓及び今後の対策について伺います。
消防局長:幸区の放火火災についての御質問でございますが、令和6年は17件の放火火災が発生しておりまして、令和5年の3件から大幅に増加いたしました。こうしたことから、放火火災が多発した8月に、警察や区役所と連携し、町内会・自治会・青少年指導員と情報共有を行い、パトロールの実施や、注意喚起ポスターを掲示するなどの対応を行ったものでございます。次に、教訓及び今後の対策についてでございますが、発生した放火火災につきましては、住宅周囲の可燃物からの出火が多かったことから、改めて放火火災防止対策としての、燃えやすいものを周囲に置かないことが大切であると再認識したところでございます。今後につきましても、関係機関や地域と連携し、住宅の周囲に燃えやすいものを置かない、ごみは決められた時間に出すなどの基本的な対策について、より多くの方々に周知されるよう、広報活動を実施してまいりたいと存じます。
しま:様々ご対応いただきありがとうございました。放火対策ついては、周知だけではなかなか協力を得られない場合もあるという声も聞きますので、関係局区と連携し、地域に寄り添った対応の検討をお願いします。次に、さらなる火災予防の取組についてです。市内では、「かわさき家庭と地域の日」に、民間施設と区、署が連携し、親子で火災対応を含めた防災訓練を実施している事例があります。そうした取組の横展開や各署等で親子で学べる取組をすることなど、また、VRを活用した火災予防の取組、ポケットティッシュの配布による啓発のところ、例えば、トラッキング現象防止グッズの配布等、既存の取組に加えて、一件でも火災件数を減らしていく取組が求められますが、本市の見解と対応を伺います。
消防局長:火災件数を減らしていく取組についての御質問でございますが、火災件数を減らすためには、関係機関や民間施設と連携し、親子で火災予防について学べる取組や、各種イベント等でのチラシや広報物品の配布など、多様な方法による広報活動が重要であると認識しているところでございます。有効な事例につきましては、各消防署で情報共有して まいりますとともに、火災を減少させるため、関係機関等と連携した取組の推進、SNSやデジタルサイネージ の活用等、より一層の火災予防の取組を行ってまいりたいと存じます。
しま:近年の本市の火災件数は、増加傾向があり、消防局の予防活動状況について質問してまいりました。広報は継続的な取組が必要であることは理解しますが、現状を鑑みますとさらなる取組が重要です。市長をはじめ、各局区におきましても積極的な取組、連携をお願いしまして、次の質問にまいります。
映像のまち・かわさき推進事業費について
しま:次に、13款1項5目映像のまち・かわさき推進事業費について伺います。令和7年度予算は、約2,166万円となっており、前年度比約20%減となっていますが、その理由を伺います。また、10年分の予算額を振り返ると、平成28年が約3,419万円以降、毎日映画コンクールが本市で開催されなくなったこともあり、減少傾向で、令和7年度は最低金額となりました。決算状況においては、ほぼ90%代後半の執行率となっている一方で、第3期実施計画中間評価施策評価シートの成果指標の「映像のまち・かわさきの取組を知っていて、評価できると回答した人の割合」において、令和5年度の目標値は27.5%に対し、実績値は11.6%であり、令和5年度事務事業評価シートにおける実施結果において、ロケ支援件数等は、目標を下回っている状況で課題です。令和7年度の取組及び今後の展望を伺います。
市民文化局長:「映像のまち・かわさき」についての御質問でございますが、本市では、市内の豊富な映像資源を活かし、企業や団体等と連携した地域活性化の取組を行うとともに、市内のさまざまな施設や場所等をロケ地として活用し、映画等の映像メディアを通して、シティプロモーションの推進、シビックプライドの醸成のほか、「KAWASAKIしんゆり映画祭」の開催などによるまちの魅力の向上を図る取組を実施しているところでございます。令和7年度予算につきましては、市制100周年記念事業である「映像タイムカプセル事業」等が終了したことを反映したものとなっております。映像のまちの取組の認知度は、映画や人気ドラマの市内でのロケ件数に大きく影響を受けることから、令和7年度に、ロケ地となりうる施設を所管する職員向けに、ロケの受入れの目的や効果等に関する研修会を実施してまいりたいと考えております。併せて、関係団体や関係局区等と連携し、市民に向けて効果的な広報を行うことで、映像のまち・かわさきの取組の認知度の向上につなげてまいります。
しま:過去の議論では、映像のまち・かわさきの取組において、映画やドラマだけでなく、アニメや漫画などの聖地巡礼等の取組についても議論がなされてきました。先日2月13日に、人気アニメのゆかりの地を観光資源とし、地域活性化を目指す「一般社団法人アニメツーリズム協会」が8年目となる「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」令和7年版を発表をしました。国内外のアニメファン約10万5千票の投票を参考に選定され、本市を舞台にした「ガールズバンドクライ」が選ばれ、本市を舞台としたアニメが選ばれるのは初めてであり、新聞等でも報道がなされたところです。私自身、主人公が住んでいる町のモデルとなっているとされる町会の住民であり、アニメ放送時から、自宅の目の前の主人公が投函したであろうポストを撮影する若者や、近所の聖地となっている神社にも同様に若い人や海外の方たちが訪れ、写真撮影しているところに遭遇することから、影響を実感しているところでありますし、地域の方々からもよくお話をいただきます。局長、職員の中にも、ご覧になっている方も多いかと思います。まず、本作品と本市のこれまでの関わりについて伺います。また、聖地の一部が穏やかな住宅街となっていますが、住民、町会等への対応状況等を伺います。
市民文化局長:「ガールズバンドクライ」についての御質問でございますが、本市の「ロケ地川崎推進事業」の委託事業者に、作品の舞台地を川崎市としたいとの連絡が制作会社からあり、候補となる施設や公園等の担当窓口の案内を行ったところでございます。作品が放送された昨年4月以降は、市内の公共施設や商店街等へのポスター掲示等の広報協力を行い、市制100周年に合わせ7月に発行した市内のロケ地を紹介する情報誌「かわさきロケーションガイド」において、本市を舞台としたアニメ作品として紹介するとともに、アニメに登場した主要スポットを併せて掲載しているところでございます。また、昨年6月に等々力球場で開催した「かわさき飛躍祭」の野外音楽イベント「かわさき100フェス」に、アニメと連動したガールズロックバンド「トゲナシトゲアリ」に御出演いただいたところでございます。作品に登場した住宅街の町内会・自治会をはじめ住民の皆様から、現時点においては特段の御意見等はいただいておりませんが、今後の状況を注視してまいります。
しま:丁寧な住民対応を引き続きお願いいたします。次に、登場する聖地のひとつである川崎駅西口の商店街の牛丼チェーン店が注目を集めています。地元商店会等との関わり等が期待されたところです。これまでも市内においてアニメや漫画の聖地とされたときがありましたが、過去の取組時の課題等をどのように改善し、活かしたのか伺います。また、今回は漫画原作のアニメ化ではなく、アニメから始まりました。得られた知見、見出した課題等について伺います。
市民文化局長:アニメにおけるロケ地活用についての御質問でございますが、ロケ地の受け入れにあたりましては、早い段階で制作会社から御連絡、御相談をいただくことが、ロケ地となる施設や地域企業等の協力、作品を活用したシティプロモーションなどの調整を進める上で有効であると考えております。「ガールズバンドクライ」につきましては、企画の段階で制作会社から情報提供があったことから、事前に調整し、「かわさきロケーションガイド」に同作品や、アニメキャラクターを無償で掲載することを御了承いただくことができたものでございます。著作権等の兼ね合いから、作品の広報には一定の制約があるところでございますが、「映像のまち・かわさき」推進フォーラムや地域企業、団体等と連携を図り、幅広い分野での情報収集を行うとともに、本市の魅力発信につなげてまいりたいと考えております。
しま:今回はアニメ制作から始まったパターンであり、早期の協力体制から様々な取組に繋がったと理解しました。予算が減少傾向ですが、シティプロモーションの推進、シビックプライドの醸成、そして本市の魅力向上という点では、意義ある事業だと思います。また、今回の訪れてみたい日本のアニメ聖地の投票数約10万5千票のうち、約半分が海外からの投票となっています。各作品の投票内訳は公表していないということでしたが、海外へのアピールにも繋がることから、アニメの取組も映像のまち・かわさきとして市民に十分理解してもらい、評価に繋げることも重要です。さらなる取組の推進をお願いいたします。
幸区区づくり推進費について
しま:次に、11款1項3目幸区区づくり推進費区の新たな課題即応事業費について伺います。令和7年度予算も引き続き、各区500万円ずつ計上されています。川崎市地域課題対応事業実施要綱に基づき、年度途中に発生する新たな課題に区長の権限で適切かつ迅速に対応するものとして理解しますが、直近3年間の幸区における執行状況及び内容について伺います。
幸区長:区の新たな課題即応事業費についての御質問でございますが、幸区における即応費の直近3年間の執行状況につきましては、令和5年度は約342万円、令和4年度は約 102万円、令和3年度は約321万円でございます。また、執行内容につきましては、主なものといたしまして、令和5年度は、令和6年1月に発生した能登半島地震を受け、首都圏での災害発生に備え、災害時に活用できるポータブル電源、ソーラーパネル、GPSロガーなどの防災対策備品を整備したところでございます。令和4年度につきましては、道路陥没事故を未然に防ぐための調査に使用する取付管調査用カメラが故障し、迅速な調査に支障を来していたため、新たな調査用カメラを購入したところでございます。令和3年度につきましては、集中豪雨の発生時に道路が冠水するおそれが判明したことから、その対策のための工事を実施したところでございます。
しま:過去には、執行率の低さや流用との線引きが曖昧ではないかとの議論もありました。改めて、「年度途中に発生する新たな課題に区長の権限で適切かつ迅速に対応するもの」とされていますが、どういった判断基準でこの予算の活用に至るのか幸区長の見解を伺います。
幸区長:区の新たな課題即応事業費についての御質問でございますが、即応費の執行に関しましては、「川崎市地域課題対応事 業実施要綱」第2条第3項に基づき、年度途中に発生した新たな課題に対して適切かつ迅速に対応する必要があると判断した場合に実施しております。この判断にあたっては、区民の生命、身体、財産等、区民生活に与える影響や緊急性のほか、課題解決の優先度や効果などを総合的に考慮し、事業を執行しているところでございます。
しま:新たな課題という意味では、課題の顕在化、顕著化もあると考えます。要綱に記載の地域の身近な課題の解決のため及び答弁の課題解決の優先度が考慮され、重要であるならば住民参加型予算という取組を提案したいと思います。住民の提案や投票によって実施事業を決めるものであり、欧州や韓国での導入から、近年では都内自治体でも実施が増えています。都内自治体では、住民から事業の提案を募集し、住民が投票によって選び、その結果を参考に事業化をしています。まちづくりを身近に感じてもらうだけでなく、インターネット投票を活用することで若い世代の需要がくみとりやすいという意見や、都内自治体の議会での議論を見ますと、職員にとっても募集された提案により、新たな発見、発想が得られるということでした。本市の令和6年人口動態では、ほとんどの年代が転出超過になっている一方、20代は約1万4千人の転入超過となり、圧倒的に多い本市だからこそ、若年層の意見を取り入れやすい環境をさらに推進し、定住に繋げ、ゆくゆくは地域活動などのまちづくりに参加してもらうことが重要と考えます。まずは、区での試験的な取組を検討すべきですが、見解と対応を伺います。
幸区長:住民による事業提案制度についての御質問でございますが、近年、一部の自治体において導入されている住民による事業提案制度につきましては、予算編成過程に住民の声を直接反映し、地域課題の解決を図るとともに、住民による行政参画を進めることを目的として、実施されているものと認識しております。幸区では、住民の声を聴く取組といたしまして、日ごろから町内会・自治会を始め、広く区民の皆様の声に耳を傾けるとともに、区民の生活意識や行政に対する意識を明らかにし区政運営及び地域課題解決の参考とすることを目的とした「幸区区民アンケート」などの広聴業務を通じて、区民のニーズを把握し、予算案に反映しているものでございます。また、区民等の提案を直接実現する取組といたしまして、区内で活動する団体が提案を行い、区と協働して地域課題の解決を図る「幸区提案型協働推進事業」を実施しているところでございます。さらに、区民の行政参画の取組といたしまして、より多くの区民の参加機会の拡充を図るとともに、多様な市民意見を聴取し地域課題の解決につなげていくことを目的として、「地域デザイン会議」を本年度から本格実施しているところでございます。これらの取組を通じて、区民のニーズを十分に把握しながら、きめ細やかな行政サービスを提供しているところでございますが、区民が区政に関心を持ち、区民自ら、「しあわせあふれる幸区」を目指して取組を進めることは、重要なことと考えておりますので、区政への更なる参画の在り方につきまして調査・研究してまいりたいと存じます。
しま:様々な手法を通じて区民ニーズの把握に努めていただいていることは理解しましたが、まだまだアプローチができていない層があると思っています。要望です。区民アンケートは幸区は2年に一回、定点で調査する重要性は理解するものの、直近5回の回答結果を見ると、結果がほぼ横ばいで変化が見られない設問も多いです。例えば、住民参加型予算ではニーズがある事業が具体的にわかるだけでなく、投票傾向や意見を付与できる投票形式にして詳細な意見を把握をし、副次的にデータやニーズの把握が可能です。フランスでは、7歳から投票ができるということで、子どもの権利条約をもつ本市にとっても意義のある取組に将来的になり得ると考えます。今回は、区の課題即応事業費の切り口で質問いたしましたが、その他関係局、部署等とも議論をさせていただきました。時期を見て、取り上げられればと思いますので、他都市状況の調査、研究、試行実施の検討をお願いいたしまして、質問を終わります。