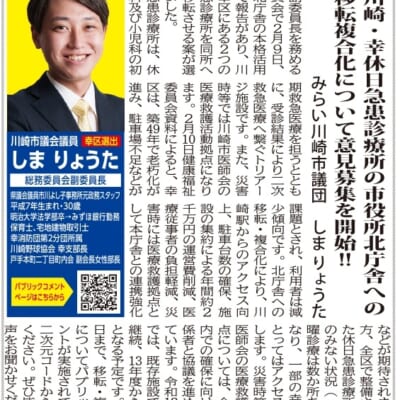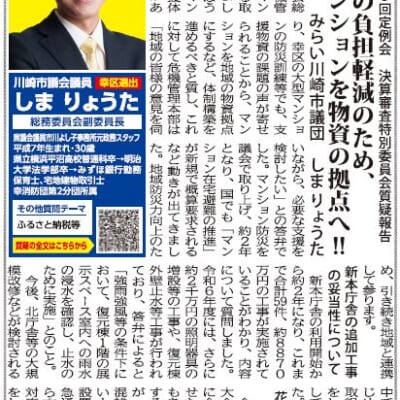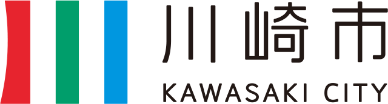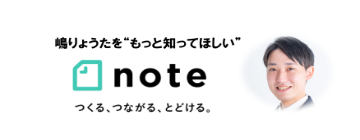令和7年第3回定例会 「総務企画局」決算審査特別委員会総務分科会
しま:2款2項4目一般管理費及び2款2項5目庁舎建設事業費について伺います。新本庁舎の利用が始まってからまもなく2年が経とうとしています。はじめに、令和6年度本庁舎で行った工事等の件数と合計金額について伺います。
また、参考に、令和5年度の本庁舎完成後と、今年度これまでの工事等の状況について伺います。
庁舎管理課担当課長:本庁舎における工事等についての御質問でございますが、工事等の件数等についてでございますが、令和6年度は14件、3,521万9,690円、令和5年度の本庁舎完成後は29件、5,260万364円、令和7年度は、現時点で、16件、880万143円となっております。
しま:答弁によると、新本庁舎完成後の工事等はこれまで合計59件、約8,870万円かかっていることがわかりました。
次に、令和6年度の工事等について伺って参ります。主な大きな工事について、具体的に伺います。また、当該工事に関連する課題について伺います。
庁舎管理課担当課長:本庁舎における工事についての質問でございますが、令和6年度につきましては、主な工事として、「川崎市本庁舎改修電気その他設備工事」を1,936万円で実施したところでございますが、この工事は、本庁舎竣工後、什器を設置した際に、照度の補強が必要な箇所を把握したことから、ダウンライト型の照明器具の増設等を行ったものであり、各諸室使用時の状況把握の必要性について、課題として認識したところでございます。
しま:当該工事は、入札情報かわさきによると、2回の入札不調があり、約1年程度遅れて実施された約2000万円の本庁舎の追加工事と認識しています。職場環境の改善という点で必要な工事だと思いますが、事前により詳細に想定されていれば、約1年も暗いと感じるということもなく、昨今の物価高騰の中、余計な支出を減らせたかと思いますので、しっかり検証をお願いします。
次に、入札情報かわさきのホームページで公表されている本市の令和6年度の軽易工事執行状況報告書によると、「川崎市役所本庁舎復元棟外壁止水等工事」がありますが、内容について伺います。
また、当該工事に関連する設計等の課題について伺います。
庁舎管理課担当課長:本庁舎復元棟外壁止水等工事についての御質問でございますが、本工事につきましては、強雨強風等の条件下において、復元棟1階の展示スペース室内への雨水の浸水を確認したことから、止水のために実施したものであり、昨今の異常気象を踏まえ、より厳しい条件下での防水性能等の検討の必要性について、課題として認識したところでございます。
しま:新本庁舎で雨漏りという話になると、いらぬ懸念をいだかせてしまうかもしれません。稀な状況下で、ということなので一定は、理解しますが、こちらもしっかりこれまでの設計など経緯含め検証をお願いします。
今回は昨年度の工事の中で、特に気になる工事等について取り上げましたが、その他の工事等についても必要性は一定理解するものの、建設時など事前に改善できなかったのかと思うものもあります。今後、北庁舎等の大規模改修など検討される中で、今回の課題等をしっかり活かしていただくようお願いします。以上です。
令和7年第3回定例会 「危機管理本部」決算審査特別委員会総務分科会
しま:2款3項1目危機管理対策費、国土強靭化地域計画推進事業費について伺います。
当初予算15,523,000円に対して執行額が995,500円で執行率が約6.4%となっていますが、要因について伺います。
また、今年度末には、次期「かわさき強靭化計画」が策定されますが、検討状況について伺います。
危機管理部担当課長:国土強靱化地域計画推進事業費についての御質問でございますが、当該事業費につきましては、新たな地震被害想定調査に向けた基礎調査を行う予定とし、令和6年度予算に計上しておりましたが、令和6年能登半島地震の発生により災害関連死が注目されるなど、地震被害想定調査の調査項目について改めて検討する必要が生じたため、国などの被害想定を把握してから行うべきものと判断し、基礎調査の実施を見送ったこと等により、執行率が低いものとなったものでございます。
次に、かわさき強靭化計画改定の検討状況につきましては、国の動向や近年の災害で発生した課題を踏まえた検討を進めており、現在、各区の自主防災組織の皆様や防災対策検討委員会からの意見も伺いながら、多様な主体との連携に向けた災害時協定の取組を拡充するなど、改定素案のとりまとめを行っているところでございます。
しま:国などの被害想定を把握してから調査を行うと理解しました。国の首都直下地震の新被害想定等の議論では、マンション防災として在宅避難に関する議論がなされ、また、本年3月にとりまとめられた「南海トラフ巨大地震対策について(報告書)」でも、マンションでの防災訓練が必要とされたところであり、先日の内閣府の概算要求では新規に「マンション在宅避難の推進」の予算要求があげられているところです。概算要求資料によると、「在宅避難を中心としたマンション防災の推進が急務」とのことです。マンションも含めた共同住宅に住む市民が多い本市において、私も令和5年12月から、議会でこれまで同様に提言してきましたが、マンション防災の取組をかわさき強靭化計画において、さらに推進すべきですが、見解と対応を伺います。
危機管理部担当課長:マンションにおける防災対策についての御質問でございますが、本市におけるマンション等の集合住宅に居住する世帯数は、令和2年度の国勢調査結果では7割を超えておりますことから、在宅避難の促進に関する取組を進めていくことは、地域防災力の向上につながるものとして重要であると考えております。このため、室内の安全性の確保や避難生活のための備蓄などについて、啓発冊子や防災に関するイベントなど様々な機会を活用して啓発を進めているほか、本年2月の地域防災計画の修正において、在宅避難の考え方の啓発について新たに記載したところでございまして、今後も、マンションの防災対策を含め、在宅避難を後押しする取組について検討してまいります。
しま:引き続き、国の動向も踏まえ、マンション防災特有の例えば、エレベーター対策、とじこめであったり、復旧訓練などの取組の検討もお願いします。
次に、関連して、令和6年度中原区ぼうさい講演会の高層マンションの防災対策の在り方についての講演及びパネルディスカッションでは、高層マンションの支援物資受援体制等について議論があったところです。地元幸区の高層マンションや大型マンションでの防災訓練等においても、避難所の支援物資をどのようにマンション住民に届けるのかなどの課題の声が寄せられます。大型マンション等に支援物資を届けるなど、体制構築を進めるべきですが見解と対応を伺います。
危機管理部担当課長:支援物資の供給についての御質問でございますが、ライフラインや市内の流通経済等の復旧の遅れなどにより避難生活が長期化する場合には、国からの支援物資等の供給が必要になるものと考えており、避難される場所によって避難所での物資の受取が困難な地域も想定されることから、複数の民間物流事業者と協定を締結し、支援物資の輸送体制を構築しているところでございます。一方で、受入れ体制として、支援物資の荷下ろし場所の設定やトラックの搬入導線の確保、物資の保管場所や上層階への運搬方法、周辺地域との連携などを、集合住宅の状況や世帯数などを踏まえ調整いただくことが必要であることから、各区と連携し、地域の皆様の意見を伺いながら、必要な支援について検討してまいりたいと考えております。
しま:実情にあった支援について検討していくとのことですので、取組を進めていただくようお願いします。
幸区内はじめを市内には防災対策など熱心に取り組まれているマンション自治会などありますので、しっかり連携、調整していただくとともに、防災資器材の補助金制度についても、現場が必要とするものがしっかり対象となるよう工夫していただくことを要望します。以上です。
令和7年第3回定例会 「経済労働局」決算審査特別委員会総務分科会
しま:7款2項1目商業振興費、市制記念多摩川花火大会事業費について伺います。
令和5年度は、4年ぶりの開催や物価高騰などにより、急遽予備費を使っての対応となりました。令和6年度の予算対応及び決算状況について具体的に伺います。
観光地域活力推進部担当課長:市制記念多摩川花火大会事業費についての質問でございますが、予算対応につきましては、コロナ禍における花火大会中止期間中に各種経費が高騰し、令和5年度開催時には、初予算に不足が生じましたが、令和6年度開催に向けましては、物価や人件費の高騰を見込んだうえで必要な予算を確保いたしました。花火大会の収支の状況といたしまして、収入につきましては、川崎市負担金が約1億7,085万円、協賛金等その他が約1,239万円、合計金額が約1億8,323万円、支出につきましては、設営等に係る費用が約1億1,416万円、花火の打上に係る費用が約3,630万円、備等その他の費用が約2,937万円、合計金額が約1億7,983万円であり、収支差額は約340万円でございました。
しま:繰越金が約340万円程度確保できたとのことです。令和6年度は市制100周年であり、内容を充実させた形で開催されましたが、一方、いわゆる通常開催となる令和7年度当初予算では、昨年度より微増の予算額となり、物価高騰等の影響が続いており、財源確保の取組強化が必須です。
次に、昨年から財源確保の取組としてクラウドファンディングが始められました。どのように評価、分析しているのか伺います。
また、課題があれば伺います。
観光地域活力推進部担当課長:クラウドファンディングについての質問でございますが、令和6年度の結果といたしましては、目標金額100万円に対して、合計99万3,500円の寄附をいただいたところでございます。令和7年度につきましても、目標金額は100万円とし、10月13日までを申込期限として実施しているところでございまして、9月17日現在では合計26万5,000円の寄附をいただいているところでございます。昨年度は市制100周年の記念大会として、特別企画などを実施し、記念映像へのお名前の掲載などを特典として設定したことから、目標金額には届かなかったもののたくさんの御寄附をいただけたものと考えております。課題といたしましては、より多くの方に関心を持っていただくことと考えておりまして、今年度からパンフレットへの掲載を行い、花火大会開催後にも寄付いただけるように期日を設定したところでございます。今年度の実施結果を踏まえ、今後の実施手法等を検討していきたいと考えております。
しま:今年度が現在4分1の程度と寄附状況が少し不安ですけれども、例えば、SNS等での開催の告知を拝見しましたが、イベント案内だけでなく、打ち上げの様子の動画とそれに加えて寄附のホームページのリンクをつけるなど、様々な手法を通じて寄附拡充を図るべきだと思いますのでお願いいたします。花火大会開催後も同様に、お願いします。
次に、関連して、国は、7月に花火大会などの大規模イベントにおける仮設トイレについて、男女で混雑の程度に差が生じないよう「バランスがとれた設置数」を求める内容の緊急通知を国内のイベント主催者に向けて出したとのことです。本市の花火大会も対象となると考えますが、対応について伺います。
観光地域活力推進部担当課長:花火大会におけるトイレについての御質問でございますが、内閣府からの文書によりますと「イベント開催時に仮設トイレを設置する場合は、男女で混雑の程度についてなるべく差が生じないよう、バランスの取れた設置数、設置エリアの工夫等をお願いします」などの記載がございまして、多摩川花火大会につきましては、男性用小便器、男女の区別をしない大便器、及びバリアフリートイレを設置しており、そのうち大便器の数を多く設置し、混雑の緩和を図っているところでございます。今後につきましても、国の動向等を踏まえて、必要な対応を検討してまいります。
しま:本市の花火大会は、男女を区別しない大便器を多く設置して混雑緩和を図っているとのことでした。引き続き、国の動向も踏まえつつ、現地の状況に合った混雑解消のさらなる取組をお願いします。以上です。
令和7年第3回定例会「財政局」決算審査特別委員会総務分科会
しま:2款2項8目財政管理費、ふるさと納税事業関係経費について伺います。令和6年第1回定例会我が会派代表質問では、寄附受入額増に向けた市長の決意を質したところ、「所管局に対し、制度の限界を見極めながら、稼げる返礼品の開発に向けて全力で取り組むよう指示している」と答弁し、後に、令和6年度、4月2日の市長記者会見で「川崎市ふるさと納税稼ぎに行きます!」と表明するなど、特に力を入れて取り組んだ1年かと思います。取組状況等について順次伺って参ります。はじめに、令和6年度は、減収額が138億円、寄附受入額は26億円となりましたが、当該事業の経費の決算状況について伺います。また、一部予備費を使用せざるをえなくなった経緯について伺います。
資金課長:ふるさと納税についての御質問でございますが、令和6年度のふるさと納税寄附受入額は、当初予算において約17億円を計上していたところ、決算では26億円余となったところでございます。また、ふるさと納税事業関係経費は寄付受入額に連動して増加するものでございまして、当初予算において約8億円を計上していたところ、決算では12億円余となったところでございます。予備費の使用につきましては、寄附が集中する年末の駆け込み需要により、寄附受入額が当初予算での見込を大きく上回り、毎月支払いを行うポータルサイト手数料や中間事業者への委託料の歳出予算に不足が見込まれたことから、支払期日が和7年2月末までのものについて、予備費を使用することとしたところでございます。
しま:年末の駆け込みの見込みが大きく上回ったため予備費を使用したとのことですが、今年度については、後ほど取り上げますけども、この9月の駆け込み需要の様子を見ながら、必要に応じた前持った対応をお願いします。
次に、令和6年第2回定例会我が会派代表質問では、ポータルサイトを利用する際の手数料の高さについて言及しました。令和6年度は大幅にポータルサイトの拡充をしてきましたが、ポータルサイトを経由した寄附受入の金額及び割合と、手数料について伺います。
資金課長:ふるさと納税についての御質問でございますが、令和6年度の寄付受入額のうち民間ポータルサイトを経由して受け入れた寄附額は、24億5千万円余で、全体の約93.5%でございます。また、ポータルサイト事業者に支払った手数料は、2億8千万円でございます。
しま:本市は寄附額に対し、大体11.4%とのことです。
次に、現地決済型ふるさと納税についてです。これまで我が会派は現地決済型ふるさと納税の導入を提言し、拡充について後押ししてきました。令和6年度から導入されましたが、昨年度、決算審査特別委員会総務分科会における我が会派委員の答弁によると、その当時で、計11店舗で導入を進めているところであり、寄附額は550万円余とのことです。令和6年度の取組結果と、今年度の取組状況について伺います。
また、課題があれば伺います。
資金課長:ふるさと納税についての御質問でございますが、令和6年度の現地決済型の寄附受入額は2,340万円余でございまして、現時点において、ふるさと応援納税電子クーポン及びPayPay商品券の利用可能店舗数は、合計で45店舗となっているところでございます。現地決済型につきましては、新しい決済手法の導入に対する店舗での負担が課題の1つでございますので、事業者負担を抑えられるような手法での対象事業者の拡大に向けて検討を進めてまいります。
次に、本市の観光施策との連携についてです。ふるさと納税の取組と観光施策は両輪で進めていくものと考えます。今年度、次期「川崎市観光振興計画」の策定が進められており、8月22日の総務委員会における「基本的な考え方について(案)」の報告では、川崎観光のメインテーマを「ヒルカワ・ヨルカワ」とし、「多面的な魅力の活用や多様な観光体験の提供を目指す」旨の方向が示され、現地決済型ふるさと納税との親和性も高いと思います。また、今年度からふるさと納税の所管課においては、人員を増やし市場分析や中長期的な戦略検討を進めているとのことです。次期「川崎市観光振興計画」においてふるさと納税に関する観点を取り入れるなど、戦略的な連携を強化していくべきと考えますが見解と対応を伺います。
資金課長:ふるさと納税についての御質問でございますが、これまでも経済労働局とは市内事業者の紹介など返礼品開発に向けて連携するとともに、観光施策の関連としては、工場夜景ツアーを返礼品とするなど、取組を進めてきたところでございます。今後のさらなる寄附受入額の拡大に向けては、観光施策との連携は重要と認識しておりますので、経済労働局を始めとした関係局との連携をより密にし、魅力的な返礼品開発に努めてまいります。
しま:ぜひ連携をより密にしていただいて、最大限の相乗効果を創り出してもらいたいと思います。引き続き注視してまいります。
次に、総務省は、「利用者に対しポイントを付与するサイトを通じて自治体が寄付を募ることを禁止する」などの制度改正を昨年発表し、今年10月からとなります。本市の制度改正に対する見解と、9月の駆け込みを含めた本市への影響を伺います。
また、9月9日総務大臣が記者会見において、記者からポイント付与の禁止の背景と意義について問われると、「公金を使用した公的な税制上の仕組みでありまして、いわゆるインターネット通販であってはならない」と発言しています。この点においては、本市と軌を一にするところだと思いますが、改めて本市の見解と今後の対応について伺います。
資金課長:ふるさと納税についての御質問でございますが、この10月に施行される改正は、制度の趣旨に沿うような抜本的な改革に繋がっていないものと考えております。そのうえで、ポイント禁止に関する報道等に伴う駆け込み需要により、本市においても、寄附受入額が本年7月までと比較して大幅に増加しているところでございます。引き続き、それぞれの見直し事項に対するポータルサイト運営事業者の対応も含めて、本市への影響を注視してまいります。また、本市では、ふるさと納税が、返礼品や節税を目当てとしたネット通販化しており、返礼品を目的とした寄附の増加により都市部における地方自治体の財政に与える影響が大きくなっていること等を踏まえ、制度創設の趣旨に沿って見直しを行うよう国に対して要請してきたところでございます。今後につきましても、国に対して制度改正に向けた要請活動を継続して行ってまいりたいと考えております。
しま:規制直前となる最近においては、複数の仲介サイトが「最大100%還元」や「ポイント5倍」といった高還元をテレビやインターネットのCM等でアピールし、駆け込み需要を加速させており、凄まじい状況です。さらなる流出も懸念され、まさに看過できない状況かと思いますので、様々な機会を捉えたさらなる要請の取組をお願いします。
今回、ポータルサイトのポイント規制がされ、ポータルサイトを利用するメリットが若干ですが薄れる中で、返礼品開発に加え、いかにリピーターなど、川崎市のファンを作っていくのかが問われる状況だと思います。手数料も高いという課題もありますから、まだポータルサイトが有効だと思いますけども、自前で集めていくということについても、他都市の状況等を注視していただいて、長期的な選択肢の一つとして持っておくことについても課題等の検討、整理を改めてしていただければと思います。以上です。
令和7年第3回定例会「臨海部国際戦略本部」決算審査特別委員会総務分科会
しま:2款4項1目臨海部国際戦略費、川崎生命科学・環境研究センター(以下、ライズ)利便施設整備事業補助金について伺います。
はじめに、本補助金の内容について伺います。
また、本補助金は、国際戦略拠点強化事業費に該当されますが、令和6年度の予算額、決算額、執行率を伺います。
また、繰越があれば、理由とともに伺います。あわせて、予算措置について伺います。
成長戦略推進部担当課長:川崎生命科学・環境研究センターについての質問でございますが、はじめに、利便施設整備事業補助金につきましては、キングスカイフロントの拠点価値の向上を図るために国際戦略拠点にふさわしい質の高い空間を提供し、安定的かつ継続的な運営を図ることを目的として、利便施設の整備費に対して補助を行うものでございます。
次に、令和6年度の国際戦略拠点強化事業費につきましては、予算現額27,866千円、決算額11,137,697円、執行率約40%となっております。予算現額と決算額の差につきましては、事業者の公募期間を当初の見込みより長く設定したことなどにより、利便施設整備事業補助金1,500万円を繰り越したものでございまして、その予算といたしましては、流用で措置したものとなっております。
しま:利便施設整備の補助であり、今回は1階の飲食店が入れ替わること対する補助と伺っています。
次に、飲食事業者選定に係る公募についてです。先ほどの答弁では、事業者の公募期間を当初の見込みより長く設定したとのことですが、公募から営業開始までのスケジュールについて伺います。
また、令和6年第2回定例会で答弁されていた事業者に対する支援について伺います。
成長戦略推進部担当課長:飲食事業者選定に係る公募についての御質問でございますが、スケジュールにつきましては、昨年の11月25日から公募を行いまして、3月に事業者を決定した上で、基本協定・転貸借契約を締結し、内装工事等の開業準備を進め、9月29日に営業を開始する予定となっております。本市としての支援といたしましては、使用料の減免は、事業者が営利企業であることなどから困難でございましたが、国際戦略拠点にふさわしい質の高い空間を提供し、安定的かつ継続的な運営に向けて、内装工事等に対する補助を行うものでございます。
しま:11月下旬に公募をして、3月に事業者の決定、要綱によると、3月下旬に契約締結とのことです。そうしたスケジュールを踏まえると、様々事情があったかもしれませんが、なおさら流用をして、繰越をするのではなく、一昨年度の予算にもあがってないものでありますから、しっかり予算要求をして予算対応した方がより適切と思いますので、指摘させていただきます。
次に、撤退されるカフェは、障害のある方が働くことを支援する施設でした。事業廃止後の活動の場などが懸念されていたところですが、就労者の方々の対応状況について伺います。
成長戦略推進部担当課長:就労支援施設のカフェレストランについての質問でございますが、本施設で以前就労されていた方々につきましては、前運営事業者が紹介やあっせんなどを丁寧に行い、他の就労支援施設などで活動していると前運営事業者から伺っております。
しま:次に、関連して、本市が支出するライズの賃料についてです。1階の一部と、2階、3階を借りていますが、現在の賃料の金額と妥当性及び、契約当初から値上げがされているのであれば、その経緯と値上げの根拠について伺います。
成長戦略推進部担当課長:LiSEの賃料についての質問でございますが、本市が支出している令和7年度の賃料につきましては、1~3階部分で年間 約3億8千万円となっております。賃料設定は、整備・運営事業者を公募した際の提案に基づき契約に定めたものであり、初期投資相当分及び維持管理相当分などを適切に積算したもので、近傍類似施設と比較しても適正であると認識しております。
賃料の見直しにつきましては、事業契約書に基づき、物価変動等を反映し、改定を行った結果、当初賃料より増額となっているものでございます。
しま:最後に要望となりますが、新しい飲食事業者につきましては、地域活動を熱心にされている事業者、店長と伺っており、とてもいいチャンスだと思います。先ほどの答弁の通り、研究施設等の賃料もかなり多額でありまして、目に見える成果がわかりにくい、または時間がかかる分野において、どう地域、市民に還元、貢献していくかが重要です。ぜひ施設関係者だけでなく、地域の拠点となるよう期待しておりますので、引き続きのフォローや、事業者、関係局区と連携して地域のためにという視点で前向きに取り組んでいただきたいと思います。以上です。